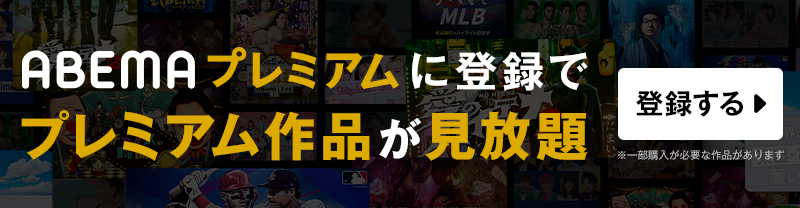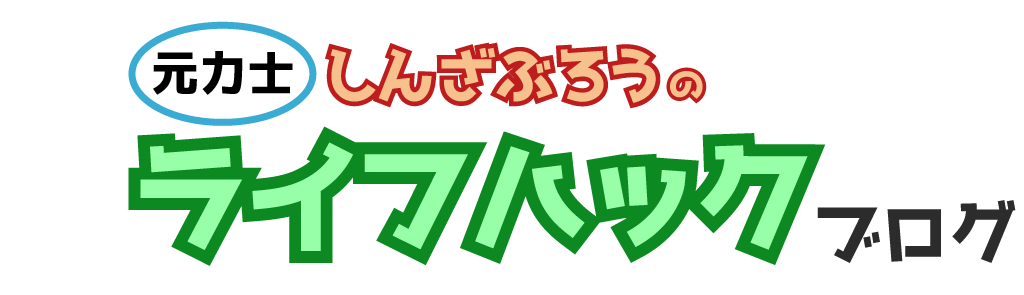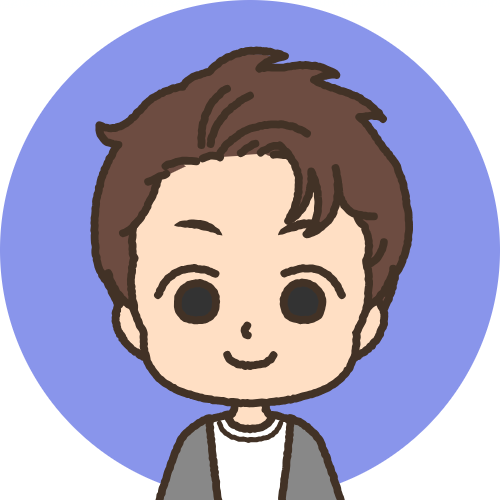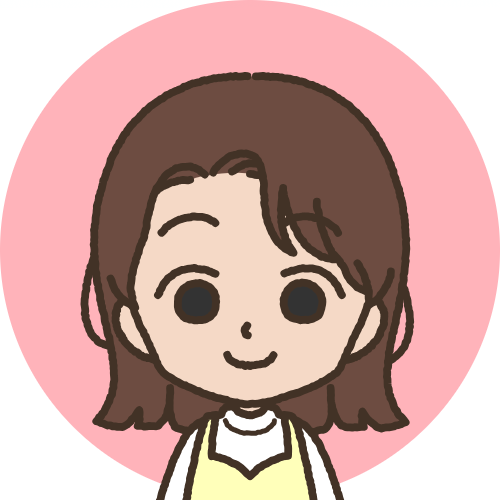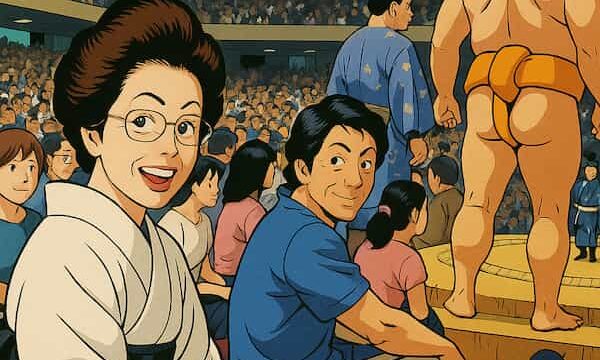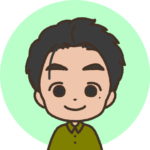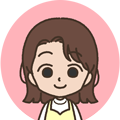相撲の太鼓は誰がたたいてる?種類・意味・音の秘密まで大解説!
本場所が始まる前日。相撲部屋には、呼出しさんが触れ太鼓をたたきに来てくれます。
その太鼓の音や口上を聞くと、「よし、明日から頑張るぞ!」って、自然と気持ちが引き締まったものです。
こんにちは!元力士のしんざぶろうです。
本場所の太鼓の音って、会場の空気をピリッと引き締めてくれるような、不思議な力がありますよね。そのリズムや音色は、力士たちの気合い、観客の高揚感とも響き合って、相撲の世界をぐっと盛り上げてくれます。
今回は、そんな太鼓に注目して、たたいているのは誰なのか、どんな種類があるのか、そして構造や素材、気になる値段の目安まで、できるだけわかりやすく紹介していきます。
ぜひ最後までお付き合いくださいね。
太鼓の音って、間近で聞くと身体にズンと響いて、とても言葉では言い表せない感覚なんだよね。あの音を聞くと、当時の本場所を迎える緊張感がよみがえってきて、なんだか懐かしくなるんだよなぁ…。
- 呼出しが太鼓をたたく理由と役割
- 太鼓には大きく3種類の打ち方がある
- 呼出しの階級制度と給料の違い
- 太鼓の構造や素材、価格の目安
- 伝説の呼出し・太鼓名人の逸話
相撲で太鼓をたたいているのは誰?

本場所や巡業で響き渡る、あの軽快で心地よい太鼓の音。いったい誰がたたいているのか、気になったことはありませんか?
この太鼓をたたいているのは、「呼出し(よびだし)」と呼ばれる、相撲の裏方さんです。
呼出しにはさまざまな役割がありますが、代表的な三大業務として知られているのが、「呼び上げ(力士の名前を呼ぶ)」「土俵づくり」、そして「太鼓」です。その中でも太鼓は、呼出しにとって大切な“技”のひとつなんですね。
太鼓の演奏には楽譜があるわけではなく、すべて口で伝わる「口譜(くちふ)」を使って覚えていきます。リズムや強弱、間の取り方などを先輩から学び、体で叩き込みながら技を磨いていきます。
最初に教わるのは伝統的な一番太鼓で、跳ね太鼓のような複雑なリズムを打てるようになるには、5年以上の修業が必要だといわれています。
太鼓担当の選び方について、明確なルールは公表されていませんが、以上のことから考えると、実際に本場所や巡業で太鼓をたたいているのは、一定以上の経験を積んだ呼出しである可能性が高いと言えるでしょう。
また、呼出しの太鼓の関係について、以下の相撲協会の公式動画が詳しく解説しています。太鼓の達人にも挑戦していて面白いので、ぜひチェックしてみてください。
呼出しの給料について
呼出しには階級があり、基本的には年功序列で昇格していきますが、実力や評価も反映されるしくみになっています。
もちろん、階級によって給料にも差があり、具体的な金額は以下の表をご覧ください。
| 階級 | 本棒(月給) | 手当(月) |
|---|---|---|
| 三役呼出し以上 | 360,000~400,000円未満 | 各人の能力・成績・勤務状況 ならびに物価・社会状勢等を 勘案し、理事長が決定する。 |
| 幕内呼出し | 200,000~360,000円未満 | |
| 十枚目呼出し | 100,000~200,000円未満 | |
| 幕下呼出し | 42,000~100,000円未満 | |
| 三段目呼出し | 29,000~70,000円未満 | |
| 序二段呼出し | 20,000~29,000円未満 | |
| 序の口呼出し以下 (3年間見習い) |
14,000~20,000円未満 |
なお、呼出しの階級制度や手当の詳細についてもっと知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

すべての太鼓をたたけるようになるまでに、5年以上も修行が必要なんて……想像以上に大変なのね。今度からは、もっとじっくり聞いてみよう♪
そして、呼出しの太鼓には、実はさまざまな場面で使用され、それぞれに意味や役割が存在します。
相撲で太鼓が使われる場面
相撲で鳴り響く太鼓は、ただの演出ではなく、それぞれにしっかりとした「意味」が込められています。たとえば、本場所の始まりや終わりを告げるもの、あるいは開催そのものを知らせるための太鼓など、場面によって役割が異なります。
ここからは、相撲で太鼓が使われる場面ごとの特徴と役割について、順を追ってご紹介していきます。まずは、本場所の前日に響く「触れ太鼓」から見ていきましょう。
触れ太鼓(ふれだいこ)
本場所の前日、土俵祭りの最後に行われるのが「太鼓祝い」です。呼出しが太鼓をたたきながら土俵を3周し、そのあと「触れ太鼓」として町へ繰り出します。これは「明日から本場所が始まりますよ」と、地域の人々に知らせるための伝統的な風習です。
とはいえ、ただやみくもに街を回るわけではありません。訪問先は決まっており、いくつかのルートに分かれて、相撲協会の贔屓筋や各相撲部屋など、関係のある家々を訪ね歩くのが慣例です。
訪問先では、太鼓をたたくだけでなく、「相撲は明日が初日じゃぞぇ~、○○山~には□□谷じゃぞぇ~」と、初日の中入り後の取組を独特の口上で伝えます。その声と太鼓の音が響くと、「いよいよ場所が始まるんだ」と実感が湧き、会場まわりにも期待と熱気が広がっていくんですよね。
以下の日本相撲協会のXでは、実際の映像が公開されています。雰囲気を感じてみたい方は、ぜひご覧になってみてください。
<大相撲三月場所>
呼出しによる触れ太鼓。
触れ太鼓とは、初日前日に太鼓を叩きながら街中を練り歩き大相撲開催を多くの人に知ってもらうために触れ回る太鼓のことを言います。大相撲三月場所は明日から!#相撲 #sumo #三月場所 #春場所 pic.twitter.com/OZkTmvmCEg
— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) March 8, 2025
街中で聞けることもあるなんて、ちょっとびっくり。触れ太鼓の呼出しさんに出会えたら、きっとラッキーね!
櫓太鼓(やぐらだいこ)
本場所の期間中、呼出しが毎日たたくのが「櫓太鼓」です。高さおよそ16メートルの「櫓(やぐら)」と呼ばれる建物のてっぺんでたたかれるのが特徴で、江戸時代から続く伝統があります。
もともとは観客を呼び寄せるための宣伝の役割があり、高い櫓の上でたたくことで、太鼓の音がより遠くまで響くように工夫されています。
なお現在では、「寄せ太鼓」と「跳ね太鼓」の2種類があり、本場所の開始と終了、それぞれの場面で異なるリズムが打ち分けられています。
1.寄せ太鼓
「寄せ太鼓」は、本場所の開始を知らせるために打たれる太鼓で、朝8時ごろに響き渡ります。リズムは「トントコトントコ」と軽快で、別名「朝太鼓」とも呼ばれています。
もともとの寄せ太鼓は、相撲協会の前身である「相撲会所」の時代、親方や関取たちを呼び集めるための合図として使われていたそうです。
相談事などがあると、太鼓の音で集会の合図を出していたんですね。まさに“呼び寄せる太鼓”という名にふさわしい役割でした。
実際に櫓から響く太鼓の音は、以下の日本相撲協会のXで公開されている映像からご覧いただけます。
<初日の様子>
令和6年最初の寄せ太鼓。#sumo #相撲 #一月場所 #初場所 pic.twitter.com/7WDK23vdT3— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) January 13, 2024
一番太鼓と二番太鼓
かつては、この寄せ太鼓が一日に二度打たれており、早朝にたたくものが「一番太鼓」、関取たちの場所入りに合わせたものが「二番太鼓」と呼ばれていました。
とくに一番太鼓には、天下泰平や五穀豊穣を祈る意味が込められており、「清めの太鼓」とも呼ばれる神聖な役割を持っていました。昔は真夜中の2時や3時に打たれていたこともあったそうです。
しかし時代とともに環境も変化し、早朝の太鼓に対して苦情が寄せられるようになったため、現在では朝8時頃に1回だけたたかれる形となっています。
2.跳ね太鼓
取組がすべて終了した午後6時過ぎにたたかれるのが、「跳ね太鼓(はねだいこ)」です。
「テンテンバラバラ」という独特のリズムで、お客さんが帰っていく様子を表現しています。
この太鼓には、「本日はご来場ありがとうございました。明日もお待ちしております」という感謝の気持ちが込められており、いわば締めくくりのあいさつのような役割を果たしています。そのため、千秋楽や一日限りの興行では打たれません。
跳ね太鼓の様子は、巡業の際に披露された「太鼓の打ち分け実演」でも見ることができます。以下の日本相撲協会のXでは、その映像が公開されているので、ぜひご覧になってみてください。
<夏巡業@釧路市>
呼出し 重夫による、櫓太鼓打ち分け実演。相撲が終わると同時に打たれる跳ね太鼓。#sumo #相撲 pic.twitter.com/QuC5qwkUFY— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) August 21, 2019
相撲で使われる太鼓の大きさ・材質・値段について

ここまで、呼出しが打つ太鼓の種類や意味、そしてそれぞれの場面での役割を紹介してきました。
寄せ太鼓、打ち出し太鼓、触れ太鼓は、いずれも相撲の風景には欠かせない存在で、あの独特なリズムと音色には、思わず心を惹かれるような不思議な魅力がありますよね。
では、その音を生み出している太鼓そのものは、いったいどんな作りになっているのでしょうか。他の太鼓と見た目は似ていても、素材や構造には深いこだわりがあります。
この章では、相撲太鼓の大きさや材質、音を生むための職人技、そして気になる値段の目安まで、順に紹介していきます。
相撲太鼓の大きさと素材
相撲太鼓は「長胴太鼓(ながどうだいこ)」という種類で、直径は約1.1尺(33cm)ほど。胴には国産のけやきが使われており、強度と木目の美しさを兼ね備えた素材です。
けやきの丸太をくり抜いた胴は、3〜5年かけてじっくり自然乾燥。その後、職人がカンナで丁寧に仕上げていきます。こうした手間をかけることで、深みのある音色と長く使える品質が生まれるのです。
相撲太鼓の音はこうして生まれる【音の秘密について】
太鼓の音色は、皮をたたいて伸ばし、音を確かめながら少しずつ調整していく作業の繰り返しから生まれます。相撲太鼓に求められるのは、張りのある高く澄んだ音が特徴。
その音を実現するには、皮を限界まで強く張る必要があり、職人の経験と感覚がものを言います。張替えの際には、呼出しが立ち会って音を確認することもあるようです。
また、太鼓を打つバチには「樫(かし)」が使われます。硬さと重みを兼ね備えているため、力強く迫力ある音が響き、遠くの観客席までしっかりと届きます。
値段はどのくらい?
相撲太鼓は特注に近い製品であるうえ、素材や工程にもこだわりがあるため、価格は安価ではないと考えられます。一般的な欅製の長胴太鼓の相場を参考にすると、数十万円、あるいはそれ以上の価格になる可能性もあるでしょう。
この太鼓を手がけているのが、東京にある和太鼓の老舗「宮本卯之助商店」です。サイトには相撲専用の太鼓こそ見当たりませんが、構造が近い長胴太鼓や和太鼓用品が多数そろっています。価格の目安もわかるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
太鼓って、正直もう少し安いのかと思ってたから、ちょっと驚いた!でも、あれだけ手間と技が詰まってるなら…高いのも納得だなぁ。
太鼓の名人【伝説の呼出し】
呼出しといえば、「呼び上げ」「土俵づくり」「太鼓」の三大業務がよく知られていますが、かつてはこれらが分業され、それぞれに専門の呼出しがいた時代がありました。
そんな分業制の中で、太鼓一筋に腕を磨き上げ、名を残した呼出しがいます。今なお「伝説」として語られる、その人物の足跡をのぞいてみましょう。
呼出太郎(よびだし たろう)1888年~1971年
1888年生まれの太郎は、11歳で相撲界に入り、若いころから非凡な太鼓の腕前で知られていました。土俵上で力士の名前を呼び上げることはせず、太鼓一筋。分業制だった当時においても、その腕前は群を抜いていたと伝えられています。
また、太鼓の技術だけでなく、人望や面倒見のよさでも知られた存在でした。大阪と東京の相撲が統合される際には、大阪の呼出し全員を東京に推挙し、さらには両国の自宅を相撲記者クラブに長年開放するなど、陰から相撲界を支え続けました。
その尽力が実を結び、1949年の五月場所では、彼の請願により呼出し16人の名前が初めて番付に掲載されることに。晩年には一連の功績が評価され、1969年秋に「勲六等単光旭日章」を受章しています。
そして、巡業や花相撲で今も披露されている「太鼓の打ち分け実演」は、太郎さんが始めたものとされています。
大阪相撲時代、巡業先での出来事。金銭的に困った太郎は、やむなく太鼓を質に入れ、代わりに空の醤油樽をたたいてその場をしのいだそうです。
それでも音に違和感を覚えた者は誰一人おらず、名人の技は道具を選ばなかった。そんな逸話が、今も伝説として語り継がれています。
まさに「弘法筆を選ばず」って感じのエピソードね♪そんなにすごいなら、太郎さんの太鼓…一度でいいから直接聞いてみたかったなぁ…。
ちなみに、最近ではイケメン呼出しも注目されているようで、話題の呼出しを紹介した記事もあります。気になる方は、こちらもぜひご覧ください。

相撲の太鼓に関するよくある質問
Q1.相撲で太鼓はどんな場面で使われますか?その種類を教えてください。
相撲で使われる太鼓は主に3種類あります。「触れ太鼓」「寄せ太鼓」「跳ね太鼓」で、それぞれ使われるタイミングや意味が異なります。
まず、本場所の前日には「触れ太鼓」が鳴らされます。これは、翌日から場所が始まることを町の人々に知らせる役目があり、呼出しが太鼓を打ちながら地域を練り歩きます。
そして本場所中には、「寄せ太鼓」と「跳ね太鼓」が毎日、高さ約16メートルの「櫓(やぐら)」の上で打たれます。
「寄せ太鼓」は朝8時ごろに打たれ、本場所の始まりを告げるもの。「跳ね太鼓」は取組終了後に打たれ、お客さんへの感謝と締めくくりの意味が込められています。
Q2.相撲太鼓のリズムはどのようなものですか?
種類によってリズムが異なります。たとえば「寄せ太鼓」は「トントコトントコ」という軽快なリズムで、本場所の始まりを知らせるものです。
一方、「跳ね太鼓」は「テンテンバラバラ」と、不規則で跳ねるような音を出して、取組終了と観客の帰りを表現しています。どのリズムも、呼出しが長年の修行で身につけた技術により打ち分けられています。
Q3.相撲中継の終了時に流れる太鼓は何ですか?
それは「跳ね太鼓」です。取組がすべて終わったあとの午後6時ごろに打たれ、お客様への「ありがとうございました」という気持ちが込められた締めくくりの太鼓です。
Q4.NHKの相撲中継の際に太鼓をたたいているシーンは観れますか?
太鼓の音は中継でも聞こえますが、たたいている姿は映りません。
なぜなら、太鼓は観客席の外にある「櫓(やぐら)」の上で打たれているため、カメラに映らない位置にあるからです。
まとめ
呼出しがたたく相撲の太鼓は、ただの音ではなく、伝統や意味、職人技が詰まった大切な存在です。太鼓の種類やリズムには、それぞれの役割があり、会場の雰囲気づくりに一役買っています。
「なんとなく聞いていた音」にも、こんな背景があるんだと思うと、次に聞くときの感じ方がちょっと変わってくるかもしれませんね。これから相撲を見るときには、力士の取り組みだけでなく、太鼓の音にもぜひ耳を傾けてみてください。
今回も、最後まで読んでいただきありがとうございました。
また、次回の記事でお会いしましょう。
相撲中継ならABEMAプレミアム一択です
「序ノ口から横綱まで、全取組を観たい」「取組後すぐに見返したい」
「解説の面白さも味わいたい」——
そんな相撲ファンにとって、ABEMAプレミアムは本当にありがたい存在です。
■序ノ口から全取組を完全中継
■広告なしでストレスゼロ
■見逃した取組もすぐ再生
■幕内以外の注目力士も毎日追える
月額1,080円(税込)で、毎場所がもっと楽しくなる。
NHKだけでは物足りない、そんな方にこそぜひ使ってほしいサービスです。