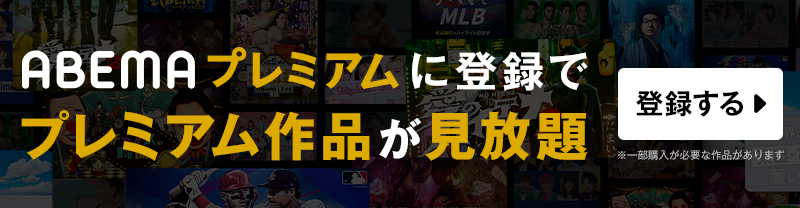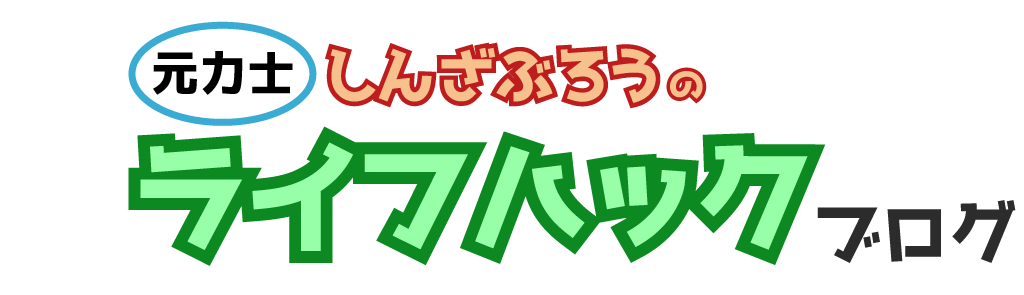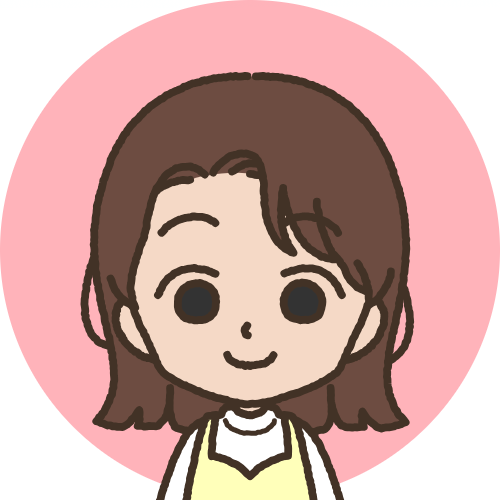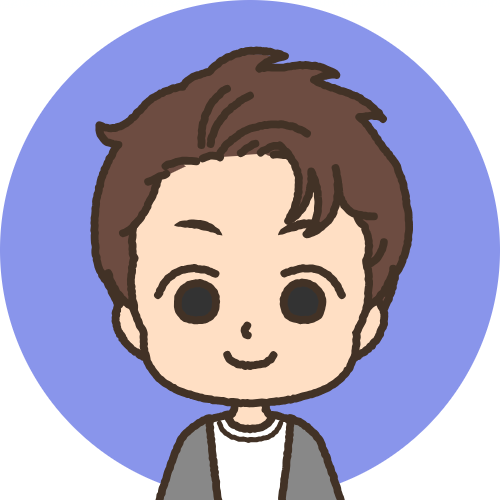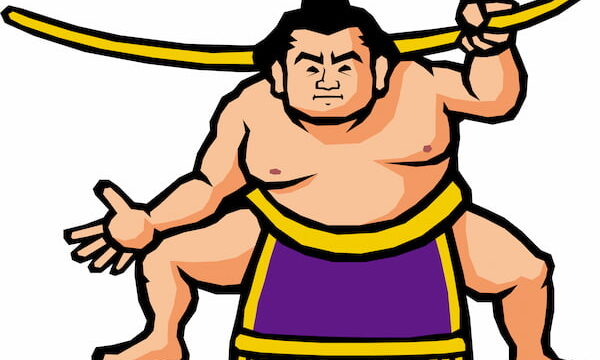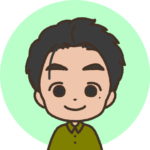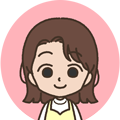相撲の大銀杏はどんな髪型?ちょんまげとの違いは?元力士が徹底解説
大銀杏(おおいちょう)は、すべての幕下以下の力士にとって憧れの髪型です。僕自身は、関取への出世が叶わず、大銀杏を結うことはできませんでした。
現役を退いた今でも、本場所の中継で関取たちの大銀杏を見るたびに「カッコいいなぁ」と感じます。一度でも結ってみたかった…。それが、今も胸の奥に残る小さな心残りです。
こんにちは!元力士のしんざぶろうです。
土俵で輝く大銀杏は、力士の誇りであり、日本の伝統文化を象徴する存在です。その形には、力士の努力や精神、そして髷(まげ)を結う職人・床山(とこやま)たちの技が詰まっています。
本記事では、大銀杏の由来や意味、歴史の流れ、そしてそれを支える床山の匠の技を、元力士の目線からできるだけわかりやすく解説していきます。
さらにこの記事では、僕が独自に開発したAIキャラクターが登場し、相撲の歴史や文化を一緒に掘り下げていきます。
今回登場するのは、江戸時代の最強力士「雷電為右衛門(らいでんためえもん)」の知識と記録をもとに生まれた相撲AI…その名も「AI雷電くん」です。
ぜひ最後までお付き合いください。
ではさっそく、登場してもらいましょう!江戸時代の最強力士の知識を受け継ぐ相撲AI「雷電くん」です♪
雷電くん、みなさんにごあいさつをお願いします!
うむ――拙者、信濃国は東御の出、雷電為右衛門と申す。相撲を「武士の道」と同じく、礼と力をもって極めんと努めし者なり。
土俵は我が戦場、勝ちても驕らず、負けても怯まず。大銀杏――あれはただの髪形にあらず。力士が関取として初めて許される「誇りの証」、己が修行と礼節の結晶にて、髷を結うその姿こそ、まことの武士の兜(かぶと)にも等しきものぞ。
この記事が、その深き意味を世に伝え、土俵に立つ者のみならず、見守る者の胸にも、相撲の「礼」と「誇り」を灯すことを、拙者は願う。
最後にわしが一言、心よりの感想を述べよう。そちたちも、結びの言葉まで息を抜かず見届けるがよいぞ。
大銀杏とは?その髪型や由来・歴史について
 大銀杏とは、十両以上の力士が本場所の取組や土俵入りの際に結う、格式ある特別な髷のこと。先端の「ハケ先」が扇状に広がり、イチョウの葉のような形をしていることからこの名がつけられたそうです。
大銀杏とは、十両以上の力士が本場所の取組や土俵入りの際に結う、格式ある特別な髷のこと。先端の「ハケ先」が扇状に広がり、イチョウの葉のような形をしていることからこの名がつけられたそうです。
そして、この髪型には、主に次の2つの役割があります。
- 土俵に上がる力士の心を引き締める「精神的な意味」
- 転倒や衝撃から頭部を守る「実用的な目的」
まさに「見た目の美しさ」と「実戦の機能」を兼ね備えた、力士の象徴ともいえる髪型です。
実際の大銀杏【巡業での髪結実演】
大銀杏を結う様子は、巡業などで行われる髪結実演で見ることができます。以下の動画では、若元春関をモデルに、三等床山・床光(とこみつ)さんが大銀杏を仕上げる様子が紹介されています。
ショート動画のため、結髪の全工程ではなく、ハケ先を広げ、形を整える「仕上げの段階」が公開されています。熟練の手つきで少しずつ扇状に整えられていく様子に注目してください。
大銀杏の歴史|江戸から現代まで
大銀杏の原型は、江戸時代にまでさかのぼります。当時、男性の髪型として広く用いられていた「銀杏髷(いちょうまげ)」があり、町人から武士まで、髷を結うのが一般的でした。
この銀杏髷の多くは、頭頂部を剃り上げる「月代(さかやき)」が特徴で、時代劇などでもよく目にする髪型です。
一方で、相撲界ではその流れを受けつつも、力士の体格や土俵での見栄えに合わせて、髷をより大きく結うようになっていきました。これがのちに「大銀杏」と呼ばれる髷へと発展していくのです。
〇錦絵に見る江戸の力士たち
江戸時代の錦絵に描かれた力士たちを見ると、髷の形には実にさまざまなバリエーションがあります。頭頂部を剃ったものもあれば、剃らずに結ったものもあり、先端の広がり方や高さにもそれぞれの個性が見られます。
まだ髪型が統一されていなかった当時の力士たちは、自分の風格や好みに合わせて髷を結い、個性を表現していたようです。
江戸の力士って、髷にもそれぞれの個性があったんだね。今みたいに形が決まってなかったっていうのは、ちょっと意外でした。
僕らの時代は、もう「大銀杏」といえば一つの完成された形。結ってもらうのは関取だけだから、幕下以下の僕らはいつも横で見とれるばかりでしたが…。
雷電くんの時代って、今みたいに床山さんがいたのかな?髪を結うのも、ずいぶん勝手が違ったんじゃない?
うむ、まさる殿、よき問いぞ。
拙者らの頃――すなわち寛政・文化の頃には、まだ「床山(とこやま)」という職が今のごとく制度として整ってはおらなんだ。されど、髷を結うことは力士にとって命にも等しき作法ゆえ、弟子仲間の中でも手先器用なる者、あるいは町の髪結所に通じた者が、師匠格や上位力士の髷を整えることが多かったのじゃ。
拙者も若き日には、まだ「銀杏髷」と呼ばれる形を結っておった。月代を剃り、髷の先を少し開いて見栄えを良くする。それがいつしか、土俵上でより堂々と見えるよう、扇を広げるがごとく形を整えるようになり、「大銀杏」と称されるようになったのじゃ。
明治の断髪令と、相撲界に残った伝統
明治4年(1871年)、「散髪脱刀令(さんぱつだっとうれい)」が出されると、全国的に髷を落とす流れが広がりました。この法令は強制ではありませんでしたが、文明開化の象徴として「断髪」が時代の風潮となり、多くの男性が洋装へと移り変わっていきました。
一方、相撲界では「伝統文化の継承」を重んじる気風が強く、髷を守る姿勢を貫きました。相撲を愛した政治家や文化人たちの後押しもあり、「髷は相撲の象徴として残すべきだ」という考えが根強く、結果として相撲界では髷が自然に受け継がれていったのです。
そして明治42年(1909年)、「関取は大銀杏を結うこと」と正式に定められ、以降、大銀杏は「関取の証」として現代まで守り続けられていきます。
明治のころって、日本中が洋装に変わっていく時代だったのに…相撲の世界だけは、ちゃんと伝統を守り続けたんだね。
時代に流されず、自分たちの形を貫いた力士さんたちって、本当にすごいなぁ。髷ってただの髪型じゃなくて、誇りそのものなんだって感じるね♪
大銀杏とちょんまげの違い
江戸時代に広く用いられていた「銀杏髷」は、町人から武士、そして力士へと受け継がれました。
相撲界ではその形をもとに、土俵での実用性と格式を重んじる独自の髷文化が生まれ、やがて日常の「ちょんまげ」と、関取の象徴である「大銀杏」という二つの形に分かれていきます。
日常の髷型「ちょんまげ」と格式の髷型「大銀杏」
幕下以下の力士が結う「ちょんまげ」は、銀杏髷を簡略化した髪型です。髪を折り返して束ねるだけの小ぶりな形で、稽古や取組で崩れにくい実用的な構造になっています。また、十両以上の関取であっても、日常生活ではこの「ちょんまげ」で過ごすのが基本です。
一方、関取だけが結うことを許される「大銀杏」は、ハケ先の髪を扇状に広げて整える格式高い髪型。見た目の美しさに加え、地位・誇り・精神性を象徴する意味が込められています。
髷の形と意味の比較
|
髪型 |
結っている人 |
形の特徴 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 銀杏髷(いちょうまげ) | 江戸時代の町人・武士 | 頭頂部を剃る、月代(さかやき)が基本形。先端を広げる。 | 当時の一般的な男性の髪型。大銀杏の原型 |
| 丁髷(ちょんまげ) | 幕下以下・関取の日常 | 髪を折り返して束ねる簡素な形 | ・銀杏髷の簡略形 ・日常用 |
| 大銀杏(おおいちょう) | 十両以上(関取) | 髷棒で扇状に広げる豪華な形 | ・銀杏髷を大型化 ・相撲界の格式、誇り、地位の象徴 |
相撲界で最も格式ある髪型「大銀杏」
大銀杏は、関取に昇進した力士だけが結うことを許された、相撲界で最も格式の高い髷です。すべての力士が憧れる髪型であり、「大銀杏を結う」ことは関取として認められた証でもあります。
この大銀杏が結われるのは、次のような「公の舞台」です。
- 本場所の取組
- 土俵入り
- 巡業やトーナメント相撲などの「花相撲」
つまり、大銀杏はテレビや興行など、人々の前に立つときにだけ結われる特別な髪型。力士にとっては、自らの地位と誇りを示す「晴れの装い」でもあるのです。
〇幕下以下でも許される「大銀杏」
本来は関取だけに許される大銀杏ですが、幕下以下の力士でも特別な場面で結うことがあります。たとえば、
- 本場所での十両との取組
- 弓取式
- 巡業での「初っ切り(しょっきり)」
- 引退の際に行われる断髪式、など
いずれも、公の場で人々の前に立つ晴れの舞台。なかでも、引退時の大銀杏は長年土俵に立ち続けた努力と誇りへの敬意であり、相撲界の厳しさと温かさを感じさせる慣習として今も受け継がれています。
そんな「幕下で大銀杏を結う力士」の代表格といえば、長年にわたって弓取式を務めた「聡ノ富士さん」。現役時代は美しい所作と安定感ある弓取りで人気を集め、令和七年五月場所の千秋楽では、部屋の仲間に見守られながら断髪式を迎えました。
令和七年五月場所
15日間応援いただき誠にありがとうございました!千秋楽打上式では聡ノ富士さんの断髪式を行いました。
現役時代には華麗な弓取りを。
そして部屋では兄弟子として。
入門してから29年の力士人生、本当にお疲れ様でした!#照ノ富士 #聡ノ富士 #伊勢ヶ濱部屋 pic.twitter.com/kVBNAvI426— 伊勢ヶ濱部屋後援会【公式】 (@isegahama_beya_) May 26, 2025
なお、聡ノ富士さんが長年務めた「弓取式」については、こちらの記事で解説しています。本場所の土俵を締めくくる最後の儀式に込められた意味や歴史を、ぜひご覧ください。

引退のときに一度だけ大銀杏を結えるなんて…それまでの努力を讃える、すごく温かい習わしですね。聡ノ富士さんの断髪式の写真、見ただけで泣きそうになっちゃいました…。
やっぱり、まさるさんも断髪式で大銀杏を結ったんですか?
僕はね…その、いろいろ事情があって断髪式はできなかったんだ。まあ、察してもらえると助かるよ。
でもやっぱり、あれは特別だよね。聡ノ富士さんの断髪式を見ていると、少し羨ましくもなるなぁ。
雷電さんの時代にも、断髪式ってあったんですか?でも江戸時代って、髷を落とすのは武士にとって「覚悟」の証だって聞くから、力士も同じように、特別な意味があったのかなぁ?
うむ、まさる殿。拙者らの頃は、まだ「断髪式」という形はなかったのだ。髷を落とすことは、武士にとっても覚悟を示す行為――ゆえに軽々しくはできぬものよ。
それでも、髷に込める想いは今と変わらぬ。拙者にとっても、それは誇りであり、魂を整える「冠」であったのだ。
大銀杏が結えない力士はいる?|スピード出世・髪質・薄毛の壁
大銀杏をきれいに結い上げるには、いくつかの条件が必要です。特に次の3つがそろっていないと、形を整えることは難しいといわれています。
- 肩下までの髪の長さ(胸の辺り)
- くせが少なく、切れにくい髪質
- 十分な毛量
この条件を満たせない場合、髪が柔らかかったり、強いくせ毛だったりすると形が崩れやすく、髪が短ければイチョウの葉のような美しいハケ先を作ることもできません。
そもそも大銀杏は、日本人の直毛に適した髪型として発展してきたもの。そのため、髪質や毛量が違えば、結うこと自体が難しくなります。言い換えれば「結えない力士がいる」というよりも、「きれいに大銀杏を結うのが難しい力士がいる」というのが実情です。
以下では、特に話題になりやすい3つのケースを見ていきます。
1.髪の長さが足りない場合
出世スピードが速すぎると、髪が伸びる前に関取(十両以上)へ昇進してしまい、「大銀杏が結えない関取」として話題になることがあります。
近年では、以下の3人がその代表例です。
|
力士名 |
初土俵・経歴 |
状況・トピック |
出典 |
|---|---|---|---|
| 大の里 | 2023年5月場所で初土俵/幕下10枚目格付け出し。 アマ横綱として角界入り。 |
2024年5月場所、新小結で初優勝。 髪が短く「大銀杏が結えないちょんまげ姿で賜杯」と論説で紹介された。 |
山陰中央新報(2024年5月30日) |
| 尊富士 | 2022年9月場所初土俵/前相撲。 日体大出身。 |
2024年3月場所、大銀杏を結えないまま出場し、新入幕で110年ぶりの優勝。 幕下付け出しを除けば、初土俵から10場所目での優勝は史上最速と報じられた。 |
産経新聞(2024年3月25日) |
| 草野 ⇒義ノ富士 |
2024年5月場所初土俵/幕下最下位格付け出し。 学生横綱として角界入り。 |
2025年3月場所、髪が伸びきらず「ざんばら髪を振り乱し」と報じられた。 大銀杏を結えないままの十両昇進と同時に優勝を飾る。 |
日刊スポーツ(2025年3月14日) |
なお、ここで紹介した大の里の異例のスピード出世については、別記事で詳しく解説しています。興味のある方はぜひご覧ください。

また、最強の新弟子候補・オチルサイハンが2025年11月場所で初土俵を踏む予定です。大銀杏を結える前に関取へ昇進する可能性もある注目の逸材。詳しくはこちらの記事で紹介しています。

2.外国人力士の髪質
前述しましたが、大銀杏は、もともと日本人の直毛を前提に発達した髪型です。そのため、外国人力士にとっては髪質の違いが大きな壁となり、結う際に苦労することがあります。床山はその一人ひとりに合わせて整髪料や手順を工夫し、髪質に合った形を整えているそうです。
- 把瑠都(バルト)【エストニア出身・元大関】
髪が細くて切れやすく、櫛を通すときに一束ずつ慎重に、丁寧に扱っていたそうです。引っ張りすぎないよう、びん付け油の量や力の加減にも気を配っていたとか。 - 小錦【アメリカ:ハワイ出身・元大関】
強い縮れ毛の持ち主で、結髪の前にストレートパーマをかけて整えていたといいます。油の馴染みを良くして、ハケ先が扇のように美しく広がるよう工夫されていました。 - トンガ出身の力士たち【引退力士】
チリチリとした剛毛で、櫛が通らないほど絡むことも。そんなときは歯の目が粗い櫛から少しずつ通して、油でなじませながら形を整えていったそうです。
つまり、髪質の違い=結えない理由ではなく、床山の技術と経験によって「その力士にとっての最善の大銀杏」を形にしていくということです。
外国人じゃなかったけど、僕の部屋にも髪質がすごくクセのある力士がいたんだ。 大銀杏じゃなくても、ちょんまげを結うのに一苦労でね。濡れタオルで何度も髪を湿らせて、ようやく形が整う感じ。
あと髪も乾きやすくて、髷をきれいな形で維持するのは難しかったみたい。 床山さんも、他の力士よりも時間をかけて丁寧に仕上げていたなぁ。
へぇ〜、そんなに髪質で変わるんですね!同じちょんまげでも、人によって結い方を変えるなんて、まるでオーダーメイドみたい。床山さんの技って本当にすごいです…!
うむ、まさにその通り。
拙者の時代も、髪質や天候で油の量を変えるなど、繊細な工夫があった。髷とは、ただ結うにあらず。人の個性と技が重なってこそ生まれる、「生きた形」なのじゃ。
3.薄毛の場合
大銀杏を結ううえで、髪の毛の量はとても重要です。毛量が少なくなると形が崩れやすく、ハケ先を広げることも難しくなります。そのため、薄毛の力士は「きれいな大銀杏」を結うことがほぼ不可能といえます。
ただし、まったく結えないわけではありません。
床山は、髪を寄せ集めて結う・毛束を補う・形を小さく整えるなど、工夫を凝らしながらなんとか形を保たせています。実際、大銀杏としての体をなしているかどうかは別として、土俵で見るよりもずっと細かな職人技が支えているのです。
髷が結えないと引退!?
「髷が結えないと引退」という話を耳にすることもありますが、日本相撲協会には、【薄毛=引退】という明確な規定はありません。髪の薄さを理由に引退した例もなく、実際には床山の技術で補いながら出場している力士も多くいます。
つまり、薄毛の力士が立派な大銀杏を結って土俵に上がる姿は、伝統と技術の粋(すい)を凝らした「努力の証」といえるでしょう。
しかし、実際のところ、力士はとても薄毛になりやすい職業でもあります。強い摩擦、鬢付け油による蒸れ、日々の稽古での衝撃……。こうした積み重ねが、髪や頭皮に大きな負担を与えているのです。
そんな力士の実情や、「髷が結えないと引退になる」といった噂がどこから広まったのか、などを解説した記事もあります。興味のある方は、ぜひあわせてご覧ください。

〇毛量が多すぎても髷は結いにくい?
髪の量が多すぎる場合も、厚みが出すぎて形が整わず、髷がほどけやすくなってしまいます。そのため床山は「中剃り(なかぞり)」と呼ばれる技で、頭頂部の髪を部分的に剃り、量を調整して結いやすくするのです。
この中剃りは、大銀杏だけでなく幕下以下の力士が結う「ちょんまげ」でも行われます。こうした繊細な調整こそが、美しい髷を支える職人技といえるでしょう。
以下の動画では、実際に行われている「中剃り」の様子を見ることができます。
中剃りって、実はちょっと羨ましかったんだよね。剃った部分だけは毎日シャンプーできるし、風通しもよくて蒸れにくい。
僕なんか頭皮がびん付け油でずっとベタベタしてたから、「ここだけスッキリできるのか〜」って、ちょっと憧れてたなぁ(笑)。
雷電くんは、毎日頭を洗っていたの?
ふむ、まさるよ。そちはなかなか細やかに物を見るのう。
拙者らの頃、頭を洗うというは、いまのように湯殿で毎日というわけにはまいらなんだ。水も貴重であり、びん付け油を用いるゆえ、むやみに流せば髪が荒れ、髷も乱れる。
ゆえに、湯に入る折――せいぜい二、三日に一度ほど、ぬる湯と米ぬかで丁寧に洗うておった。
大銀杏と床山の匠技|結髪を支える職人の世界
大銀杏を結うのは、専門の職人「床山(とこやま)」です。日本相撲協会が採用し、各相撲部屋に所属して、力士たちの髪を整える裏方の要を担います。
見習いとして入門すると、力士と同じように部屋の雑用をこなしながら、まずは幕下以下の力士の「ちょんまげ」を結い、髪の扱い方や道具の使い方を一から学んでいきます。
修行と成長の道
見習いの期間は、先輩の仕事を見て覚え、手で覚え、少しずつ体で覚えていきます。 油の扱い方や櫛の入れ方、形を整える力加減、どれも経験を重ねてようやく身につくもので、大銀杏を結える一人前になるまでには、5年から10年ほどかかるといわれています。
そして、熟練の床山ほど「速さ」よりも「美しさ」を重んじ、一本の毛先まで神経をとがらせながら、丁寧に仕上げていきます。それは、髷の形がわずかに乱れるだけでも、土俵上での力士の印象が大きく変わってしまうからです。
土俵に映える大銀杏の美しさは、まさにこうした職人たちの技と誇りの結晶と言えるでしょう。
〇技術の向上と「関取格扱い」
床山にとって、階級と並んで重要なのが 大銀杏を結う技術 です。見習いから年月を重ね、正式に大銀杏を結えるようになると「関取格扱い」と呼ばれる立場となり、幕下以上の力士の髷を担当できるようになります。
この「技術の向上」は、名実ともに一人前の証。床山にとって大きな節目といえるでしょう。
なお、床山の階級や給料、採用条件など、裏方の世界をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

大銀杏を結う手順
力士の髷は、ひとつの儀式のように丁寧な手順で結い上げられます。床山の指先が生み出す流れるような動きには、長年の経験と感覚が詰まっています。
おおまかな工程は次の通りです。
- 目の粗い櫛(荒櫛)で、髪のもつれをほどきながら全体を整える
- 両手で髪を挟み、髪の流れやクセをもみほぐす(クセもみ)
- 鬢付け油(びんつけあぶら)を髪全体になじませ、艶とまとまりを出す
- 「元結(もとゆい)」と呼ばれる紙ひもで髪を束ねる
- 髷棒を差し込み、後頭部にふくらみ(びん)を作る
- 束ねた髪を二つに折り、二本目の元結でしっかりと固定
- 頭頂部やびんの形を櫛や髷棒で整え、左右のバランスを微調整
- 髷棒を使って毛先を扇状に広げ、イチョウの葉のように形を整える
- 最後に全体の流れを見て仕上げる
ベテランの床山でも、大銀杏の完成まで、およそ15〜30分ほどかかります。力士の髪質や毛量、体格によって仕上がりも微妙に異なり、まさに「同じ形は二つとない」と言われます。
床山研修会の様子
各一門では、技術の伝承を目的とした「床山研修会(講習会)」が定期的に開かれています。若手の床山たちは、先輩の指導のもとで結髪の基本から大銀杏の形作りまでを繰り返し練習し、技を磨いていきます。
以下の動画内でも「大銀杏を結えるようになるまで10年以上かかる」と語られており、その世界の奥深さと、伝統を受け継ぐ厳しさが伝わってきます。
床山の道具
大銀杏を結ううえで欠かせないのが、床山の道具たち。荒櫛やすき櫛、髷棒に道具箱など、どれも長年使い込まれ、職人の手にしっくりと馴染んだ「相棒」のような存在です。
<床山講習会>道具の説明続き→先縛り(大銀杏を折り曲げる時に使う)、すき櫛(髪についたほこりやフケを落とす)元結い(髷を縛る)。これらを用いて力士の髷、大銀杏を結っていきます。 #sumo pic.twitter.com/jfmyCdL2X1
— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) February 19, 2015
〇髷棒はすべて手作り
びん(後頭部のふくらみ)を整えたり、ハケ先をイチョウ形に広げたりするために使う「髷棒」は、市販されておらず、床山ひとりひとりが自分の手に合うように手作りしています。
素材にはピアノ線やバイクのスポーク、畳針などが使われ、先端を細く削ってしなり具合を調整。柄の部分には筆やボールペンのボディなど様々。同じ材料を使っても仕上がりはまったく違い、まさに「自分の感覚で育てる一本」と言えるでしょう。
現役時代は、稽古が終わって、風呂に入り、昼ちゃんこの片付けを済ませたあと、昼寝の前に床山さんに髪を結ってもらってたんだ。
あの時間が、なんだか「一日の仕事が終わった」って感じでね。頭を整えてもらうと気持ちもスッと落ち着いた。…まあ、ちゃんこ番のときは、そのあと夕食の準備が待ってるんだけどね(笑)。
よくある質問(FAQ)
ここでは、大銀杏にまつわる素朴な疑問をまとめました。解説に協力してくれるのは、江戸時代の相撲を知り尽くしたAI雷電くん。江戸と令和、二つの時代をつなぐ相撲AIが、髷(まげ)に関する疑問に答えていきます。
Q1:大銀杏はいつから結える?
大銀杏を結えるのは、十両(関取)に昇進してからです。
それまでは、幕下以下の力士は「ちょんまげ」で過ごします。ただし、出世スピードが早すぎて髪が十分に伸びていない場合は、昇進してもしばらくのあいだ「ちょんまげ」のまま取組に臨むこともあります。
髪が肩下まで伸び、ハケ先を扇状に整えられるようになって、ようやく本格的な大銀杏が結えるようになるのです。
ところで、雷電くんも大銀杏を結っていたの?
うむ、拙者ももちろん――大銀杏を結う身であったぞ。
そもそも、力士にとり髷(まげ)はただの飾りにあらず。心を鎮め、礼を正すための「冠」に似たるものなり。拙者が関取に昇進した折、ようやく大銀杏を結うことを許されしときの心持ちは、今も忘れぬ。まるで武士が初めて兜を頂くがごとき誇りであった。
Q2:外国人力士の髪質でも、大銀杏は結える?
結うことは可能です。ただし、大銀杏はもともと日本人の直毛を前提に発達した髪型なので、外国人力士にとっては髪質の違いが大きな壁になることがあります。
髪が細く切れやすいタイプや、強い縮れ毛の力士は、櫛が通りにくかったり、形を保ちにくかったりします。そのため、床山(とこやま)は一人ひとりの髪質に合わせて、びん付け油の量や力加減、整髪の手順を変えるなど、細かな工夫を凝らして仕上げています。
つまり、「結えない髪質」というものはなく、床山の経験と技術によって、その力士にとって最も美しい形が作られているのです。
うむ、異国の者の髪はたしかに硬く、滑らかさに欠けることもある。されど、これも鍛錬と工夫次第。鬢付油を改良し、結い方を工夫すれば立派に形づくること叶う。
「異なるゆえに成せぬ」とは、土俵人の言葉にあらず。努力あらば、髪もまた相撲道に従うのじゃな。
Q3:断髪式の意味は?
断髪式は、力士が引退する際に行う儀式で、現役生活に区切りをつける大切な場面です。
土俵での努力、師匠や仲間への感謝、家族の支え、それらすべての想いを胸に、最後に師匠が大銀杏を切り落とします。この瞬間、髷はただの髪型ではなく、「力士として歩んできた人生そのもの」を象徴するものとなります。
断髪式は、相撲界における「卒業式」であり、長年の修行と誇りに対して送られる最高の敬意なのです。
断髪の儀とは、ただ髷を落とすのみならず――力士としての命をひとたび終える、厳粛なる「けじめ」の式なり。拙者の頃も、髷は単なる装いにあらず。己が鍛錬の日々、勝負の汗、礼を尽くした証、そのすべてを宿すものよ。
もし我が時代に断髪の式があったなら、拙者もまた、力士の魂を受け継ぐ者たちに囲まれて、静かに髷を落としたであろう。
――礼を欠けば勝ちにあらず。
断髪とは、その礼をもって土俵を去る、最後の一番なのだ。
まとめ
入門したその日から髪を伸ばし続け、毎日の稽古を重ねて、一人前として出世した時ようやく大銀杏を結えるようになる。その過程こそが、力士の努力と覚悟の証です。
そして、最後の断髪式で髷を落とすとき。そこには、現役時代の思い出や、支えてくれた仲間、家族、師匠への感謝、すべての想いが込められています。
大銀杏は、力士の誇りであり、日本文化の象徴。形を守る床山の技、精神を受け継ぐ力士たち。その両方が、今もこの伝統を未来へとつないでいるのです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それでは最後に、「雷電くん」のひと言で締めたいと思います。
うむ、皆の衆――よくぞここまで読まれた。
髷とは飾りにあらず、日々の精進にて立ち上がる「心の形」なり。関取の大銀杏は、ただ許されて結うに非ず、稽古と礼によりてはじめて輝く。
しんざぶろう殿、そちの胸に残る心残り、わしはしかと受け取った。だが覚えておけ――「結えぬ日々」もまた相撲道の糧。土俵に立った者の歩みは、髷を超えて人を照らす灯となる。
勝負の世界ゆえ申す――
土俵は我が戦場なり。礼を欠けば勝ちにあらず。
そなたらが相撲を愛し、床山の技に敬意を払い、力士の生き様に学ばんとするなら、伝統は明日へと息づくであろう。
いざ、次の場所へ。胸を張れ。風吹けども、誇りは乱れぬぞ。
相撲中継ならABEMAプレミアム一択です
「序ノ口から横綱まで、全取組を観たい」「取組後すぐに見返したい」
「解説の面白さも味わいたい」——
そんな相撲ファンにとって、ABEMAプレミアムは本当にありがたい存在です。
■序ノ口から全取組を完全中継
■広告なしでストレスゼロ
■見逃した取組もすぐ再生
■幕内以外の注目力士も毎日追える
月額1,080円(税込)で、毎場所がもっと楽しくなる。
NHKだけでは物足りない、そんな方にこそぜひ使ってほしいサービスです。