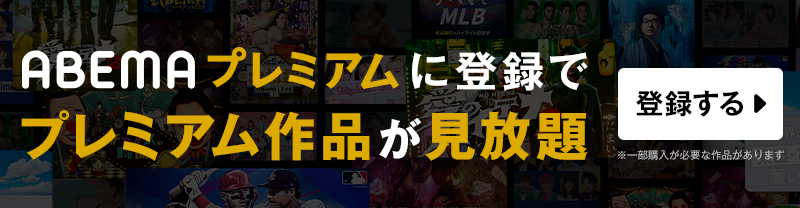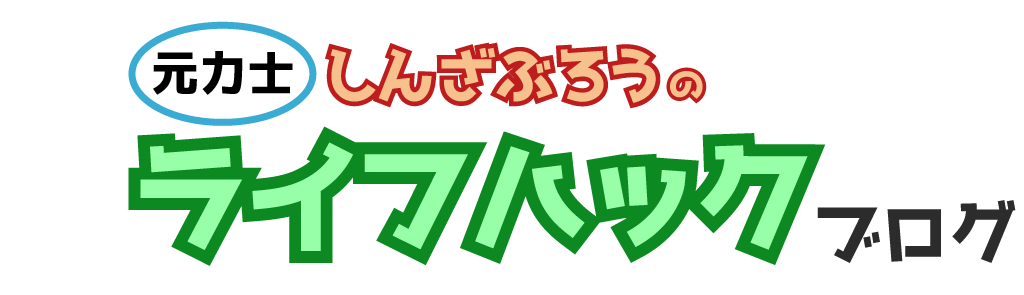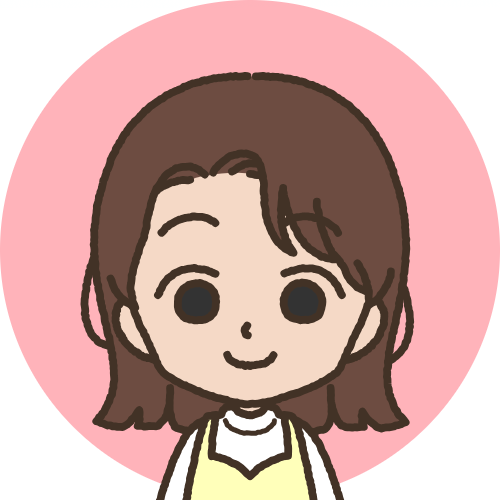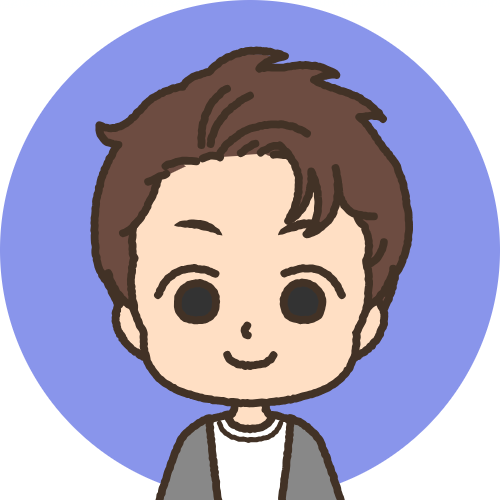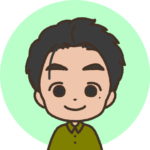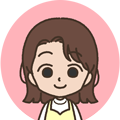三重ノ海剛司の現在は?横綱時代から館長までの軌跡も辿っていくよ!
今回、三重ノ海剛司さん(以下敬称略)の星取表を見返しましたが、序二段時代は特に目立った成績がなかったことに驚きました。それでも横綱まで登り詰めた姿を知ると、粘り強い努力が大切だと改めて感じさせられますね。
元力士のしんざぶろうです。こんにちは!
今回は、三重ノ海の現在の状況に迫りつつ、彼の歩んできた相撲人生を振り返ります。彼は第57代横綱として活躍したあと、引退後も親方や理事長、相撲博物館の館長として多大な功績を残してきました。
この記事では、三重ノ海の現在の状況や家族の活躍に触れながら、現役時代の偉業、親方としての指導、さらに相撲協会の理事長としての功績に至るまでの軌跡を辿っていきます。
相撲ファンならずとも、彼の粘り強さと情熱には驚かされること間違いなしです。それでは、三重ノ海の魅力に迫っていきましょう!
ぜひ最後までお付き合いくださいね。
横綱としてだけじゃなくて、理事長としても相撲界に貢献していたのね!現役力士にばかり注目してたから、知らなかったわ。
- 家族とのプライベートな側面と最近の近況
- 三重ノ海剛司の横綱としての功績と引退後の活動
- 武蔵川親方として弟子を育成した実績
- 日本相撲協会理事長としての改革と不祥事対応
- 相撲博物館館長としての文化普及への貢献
三重ノ海剛司の現在は?

三重ノ海剛司は、2023年2月に75歳で相撲博物館の館長を退任する意向を示し、長年にわたる相撲界での貢献に一区切りをつけました。
彼は約60年間にわたり、力士としてだけでなく、引退後も相撲文化の普及や保存に尽力してきました。三重ノ海が築いた博物館の運営体制は引き継がれ、今後も相撲文化の保存と発展に寄与し続けるでしょう。
退任後も彼は相撲界に強い影響を与え続け、弟子たちの成長を見守りながら、自身の経験を基にした指導を続けています。健康状態も良好で、家族との時間を大切にしながら静かな生活を送っていると報じられています。
また、相撲界のニュースにも関心を持ち、弟子や後輩力士たちの活躍を喜んでいるとのことです。今後も彼の存在は相撲界にとって重要であり続けるでしょう。
ちなみに、三重ノ海の館長退任について、読売オンラインでも記事になっています。以下のリンクから確認できますので、興味がある方は読んでみてください。
家族とプライベート
三重ノ海剛司の家族は、多方面で注目を集めています。
彼の長男、石山俊明さんは元力士で、三段目まで昇進後に引退。その後は俳優として活動し、テレビドラマ『GTO』や『暴れん坊将軍』に出演するなど、相撲界とは異なる道で成功を収めました。
さらに、三重ノ海の孫である嵐翔真(あらし しょうま)さんも話題です。
(石山俊明さんの息子であるかは不明)
嵐翔真さんは2024年、「第39回メンズノンノモデルオーディション」で準グランプリを受賞し、同誌の専属モデルに選ばれました。17歳でありながら、身長190cmという恵まれた体格を活かし、モデル業界で注目されています。
嵐翔真さんがモデルの道を志した理由は、俳優の阿部寛に憧れていたからです。幼少期には相撲や水泳にも取り組んでいましたが、阿部さんが「メンズノンノ」のモデルだったことを知り、モデルの世界に挑戦する決意を固めました。
オーディション後にはInstagramで感謝の気持ちを表明し、今後はサーフィンやバイクなどの趣味を通じて、渋くてカッコいいモデルを目指すと意気込んでいます。
嵐翔真さんのキャリアはまだ始まったばかりですが、専属モデルとしての今後の活躍が非常に期待されています。
なお、嵐翔馬さんの「メンズノンノ専属モデル」の件は、Yahoo!ニュースでも取り上げられました。以下がリンクになりますので、気になる方はチェックしてみてください。
さくら
家族も違う分野で活躍しているのね♪
でも、近況はわかったけど、三重ノ海さんって横綱時代にはどんな力士だったのかな?
それではここからは、改めて「三重ノ海」が相撲界にどのような功績を残したのか、横綱時代から相撲博物館館長までの実績を振り返っていきましょう。
横綱:三重ノ海剛司の基本情報
三重ノ海剛司(みえのうみ つよし)(本名:石山五郎)は、1948年2月4日生まれ、三重県松阪市出身の元大相撲力士で、出羽海部屋に所属していました。第57代横綱として広く知られています。
彼は1963年7月に初土俵を踏み、1969年9月に幕内に昇進。1979年9月場所で横綱に昇進し、1980年11月に現役を引退しました。主な成績は以下の通りです。
- 最高位: 第57代横綱
- 生涯戦歴: 695勝525敗1分56休(105場所:勝率.570)
- 横綱戦歴:55勝23敗30休(8場所:勝率.705)
- 大関戦歴:180勝123敗12休(21場所:勝率.594)
- 幕内戦歴:543勝413敗1分51休(68場所:勝率.568)
- 優勝回数: 幕内最高優勝3回(全勝1回)、三段目優勝1回
- 三賞受賞: 殊勲賞5回、敢闘賞1回、技能賞3回
三重ノ海剛司の現役時代
1963年に初土俵を踏んだ三重ノ海ですが、長い相撲人生の中で多くの困難に直面しました。特に体格や経験に恵まれず、序二段時代には「お前は稽古しないで日向ぼっこしていろ」と言われたこともあるほど。普通なら挫折してしまいそうな状況ですが、彼は諦めず、努力を重ねて少しずつ力をつけていきました。
1970年には新三役として初めて小結に昇進。このとき、横綱大鵬を破るという大きな偉業を成し遂げ、一気に注目を浴びました。その後、1976年には幕内初優勝を達成し、27歳11か月という年齢で大関に昇進。まさに順風満帆な時期でしたが、すべてが順調に進んだわけではありません。
新大関としての最初の場所では、怪我に悩まされ、2度も途中休場を余儀なくされました。その結果、大関の地位を失ってしまいます。しかし、ここで再び努力を重ね、翌場所で見事に10勝を挙げて特例で大関に復帰。彼の粘り強さと諦めない姿勢が、再び大関の座を掴む原動力となりました。
1979年9月場所で、ついに彼は横綱に昇進します。当時31歳5か月という、横綱昇進としては遅咲きでしたが、それでも横綱として2度の優勝を果たすという立派な成績を残しました。特に、1979年の九州場所では若乃花との取り組みがNHKの視聴率39.8%を記録し、多くの相撲ファンの心を掴んだのです。
そして、1980年11月場所をもって引退。横綱としての在位期間は短かったものの、その功績は今なお多くのファンの心に深く刻まれています。
- 初土俵から幕内昇進まで: 三重ノ海剛司は1963年7月に初土俵を踏み、体格や経験に恵まれない中で努力を重ね、1970年に小結に昇進。横綱大鵬を破り注目を浴びる。
- 大関昇進と苦難: 1976年に幕内初優勝を果たして大関に昇進するも、怪我により2度の途中休場で大関の地位を失う。翌場所で10勝を挙げ、特例で大関に復帰。
- 横綱昇進と活躍: 1979年9月場所、31歳5か月という高齢で横綱に昇進し、横綱として2度の優勝を果たす。1979年の九州場所では若乃花との取り組みがNHKの視聴率39.8%を記録し話題を集めた。
- 引退: 1980年11月場所をもって現役を引退。横綱としての在位はわずか8場所と短かったものの、2度の優勝を果たし、その活躍は多くの相撲ファンに強い印象を残した。
なお、横綱の昇進条件や品格に関して、以下の記事でくわしく解説しています。横綱に興味がある方は、こちらもチェックしてみてください。

武蔵川親方時代
三重ノ海剛司は引退後、年寄名「武蔵川」を襲名し、1981年に武蔵川部屋を創設しました。彼は厳しさと愛情を兼ね備えた指導で知られ、多くの優れた力士を育て上げました。
親方としての指導力は非常に高く評価されており、相撲界全体に大きな影響を与え続けています。特に注目すべき弟子として、以下の3人が挙げられます。
武蔵丸光洋
武蔵丸光洋は、ハワイ出身の力士で、1989年に大相撲に入門しました。初土俵からわずか2年で幕内に昇進し、1994年には大関、そして2000年には第67代横綱に昇進しています。横綱時代にはその巨体と力強い取り口で多くのファンを魅了し、幕内最高優勝を12回達成するなど、輝かしい成績を残しました。
また、通算連続勝ち越し記録55場所という歴代1位の記録も保持しています。2003年に引退後は、武蔵川部屋の親方として後進の指導に尽力し、タレント活動にも取り組んでいます。武蔵丸光洋は、実績はもちろん、その人柄でも多くのファンに愛された力士です。
武双山正士
武双山正士は、茨城県水戸市出身の力士で、1993年に大相撲に入門しました。幕下付出でデビューした彼は、2場所連続で全勝優勝を果たし、十両へ昇進。
その後、1993年9月場所で入幕、さらに、2000年5月場所からは東大関に昇進し、大関として27場所も在位。安定した実力を示しました。成績も優れ、生涯戦歴は554勝377敗122休。幕内最高優勝を1回達成し、三賞を合計13回受賞しています。
2004年に現役を引退後は、藤島親方として後進の指導に尽力。また、日本相撲協会の副理事を務めるなど、相撲界において大きな影響力を持っています。
出島武春
出島武春は石川県金沢市出身の力士で、1996年3月場所に幕下付け出しで初土俵を踏みました。わずか1年後の1997年3月場所で新入幕を果たすなど、急速に昇進していきます。
出島の大きな転機は、1999年7月の名古屋場所で関脇として13勝2敗の成績を挙げ、幕内最高優勝を達成したこと。この優勝で大関昇進が決まりましたが、幕内優勝は関脇時代の1回のみです。大関として12場所在位し、三賞も合計10回受賞しました。
2001年には怪我で大関の地位を失いましたが、その後も48場所にわたり現役を続け、2009年7月場所で引退。引退後は年寄「大鳴戸」として後進の指導に当たっています。
すごいわね!
横綱や大関をこんなにも輩出しているなんて!
彼の指導スタイルは、厳格さと弟子たちの個性を尊重するバランスを取り、各力士が持つ強みを最大限に引き出すものでした。武蔵丸や武双山、出島といった弟子たちが相撲界で大成したのは、まさに三重ノ海の指導力の賜物です。
ただ、親方としての活躍の中で困難もありました。弟子である雅山哲士が大相撲野球賭博問題に関与した際には、三重ノ海も監督責任を問われることになりました。それでも、彼の指導者としての評価が揺らぐことはなく、相撲界での影響力は変わらず大きなものでした。
その後、彼はさらに大きな役割を担うことになります。
次は、日本相撲協会での理事長就任と不祥事への対応について触れていきます。
日本相撲協会での理事長就任と不祥事への対応
三重ノ海剛司は、2008年9月8日に第10代日本相撲協会理事長に就任。理事長として、相撲協会の透明性を高めるため、財務や運営方針の情報公開を推進し、信頼性の向上に努めました。
不祥事への対応
彼が理事長に就任した当時、相撲界では多くの不祥事が相次いでいました。2007年の時津風部屋での力士暴行死事件や、大麻問題などが社会的に注目される中、三重ノ海は厳しい対応を迫られました。外部役員を協会に迎え入れるなど、相撲界の閉鎖的な体質の改善に尽力しました。
野球賭博問題と辞任
2010年には大相撲野球賭博問題が発覚し、三重ノ海の弟子である雅山が関与していたため、監督責任を問われることになりました。これを受け、彼は2010年7月4日から25日まで謹慎処分を受け、理事長職を一時的に離れます。
謹慎期間中は、村山弘義が理事長代行を務め、三重ノ海自身は高血圧と胃がんの治療のため入院しました。病状は回復せず、8月5日に理事長職に復帰したものの、2010年8月12日に正式に辞任を表明します。
この辞任の背景には、理事長としての責任だけでなく、健康上の問題が大きく影響していました。彼の後任には17代放駒親方(元大関・魁傑)が就任しました。
理事長としての評価
一連の不祥事への対応は、三重ノ海の理事長としてのキャリアに大きな影響を与えました。しかし、彼の改革姿勢や相撲協会への貢献は広く認められており、困難な状況下でも協会の透明性向上や若手力士の育成に尽力した点は高く評価されています。
- 理事長就任: 三重ノ海剛司は2008年9月8日に第10代日本相撲協会理事長に就任。
- 改革への取り組み: 財務や運営方針の情報公開を進め、協会の透明性と信頼性を高めた。
- 不祥事対応: 理事長就任時に相撲界では不祥事が続発しており、特に2007年の暴行死事件や大麻問題に対して厳しい対応を取った。
- 野球賭博問題: 2010年に発覚した大相撲野球賭博問題で、弟子の雅山が関与し、三重ノ海も監督責任を問われ、謹慎処分を受けた。
- 辞任の経緯: 高血圧と胃がんの治療のため、2010年7月から一時的に理事長職を離れ、8月12日に正式に辞任。
- 理事長としての貢献: 不祥事の中でも、相撲協会の改革や若手力士の育成に尽力し、その姿勢は広く認められている。
相撲博物館館長としての活動
2013年2月3日に日本相撲協会を停年退職した三重ノ海剛司は、同年に相撲博物館の第6代館長に就任しました。以降、2023年までその職を務め、相撲文化の普及と保存に大きく貢献しました。
館長としての活動期間中、展示や教育プログラム、そして地域社会との連携を通じて、相撲の魅力を幅広く伝える取り組みを積極的に展開。相撲の歴史や伝統を後世に伝えるための様々な企画を推進し、多くのファンや一般の人々に相撲文化の重要性を伝えました。
館長としての功績を以下の4点にまとめました。
展示企画と特別展
三重ノ海は、相撲博物館の展示内容の充実に力を入れ、相撲の歴史や著名な力士に焦点を当てた特別展を企画しました。
例えば、「第19代横綱 常陸山」の特別展では、当時の資料や愛用の品々を展示し、その偉業を来館者に伝えることで、相撲の深い文化的背景を広めました。彼のこうした展示企画は、相撲ファンのみならず、一般の来館者にも相撲の歴史と魅力を効果的に届けるものでした。
教育プログラムと地域社会との連携
三重ノ海は、地域社会や学校との連携にも注力し、子どもたちや若者に相撲の精神や技術を伝える教育プログラムを実施。
これにより、次世代への相撲文化の継承に努め、相撲の技術や精神を学ぶ機会を提供しました。特に子ども向けのワークショップや体験イベントを通じて、相撲への興味を喚起し、次世代のファンを育てることに貢献しました。
相撲協会との連携と財務管理
相撲博物館の運営において、三重ノ海は日本相撲協会との連携を強化し、博物館の持続的な運営のために財務管理や資金調達も積極的に行いました。必要な支援や助成金の確保に向けた交渉や予算管理を担当し、博物館の健全な運営に寄与しました。
メディア活動と相撲文化の普及
また、三重ノ海はメディアへの出演や講演活動も通じて、相撲の魅力や自身の経験を語り、相撲文化の普及に尽力。相撲が持つ伝統的な価値やその現代的な意義について広く発信し、社会全体への理解と関心を高めました。
三重ノ海は2023年に館長を退任しましたが、その間に築き上げた博物館の運営体制と文化普及への貢献は、今後も続くことでしょう。彼の活動は、相撲界のみならず、日本文化全体への重要な影響を与えました。
ちなみに「相撲と故郷」と題して、三重ノ海剛司が読売新聞オンラインで自身の相撲人生について連載で語っています。彼の経験や相撲への思いをより深く知りたい方は、ぜひ下記のリンクもチェックしてみてください。
元力士 まさる
まとめ
三重ノ海は、力士としての現役時代から親方、理事長、そして相撲博物館館長として、常に相撲界の発展に尽力してきました。特に厳しさと愛情を持って弟子を育て、相撲文化の普及に努めたその姿勢は、多くの人に影響を与え続けています。
今もなお、弟子たちの活躍を見守りながら、相撲への情熱を持ち続ける三重ノ海。彼の貢献は今後も相撲界にとって重要なものとなるでしょう。皆さんもぜひ、彼の歩んだ道に思いを馳せてみてくださいね。
今回も、最後までお読みいただきありがとうございました。
また、次回の記事でお会いしましょう。
相撲中継ならABEMAプレミアム一択です
「序ノ口から横綱まで、全取組を観たい」「取組後すぐに見返したい」
「解説の面白さも味わいたい」——
そんな相撲ファンにとって、ABEMAプレミアムは本当にありがたい存在です。
■序ノ口から全取組を完全中継
■広告なしでストレスゼロ
■見逃した取組もすぐ再生
■幕内以外の注目力士も毎日追える
月額1,080円(税込)で、毎場所がもっと楽しくなる。
NHKだけでは物足りない、そんな方にこそぜひ使ってほしいサービスです。