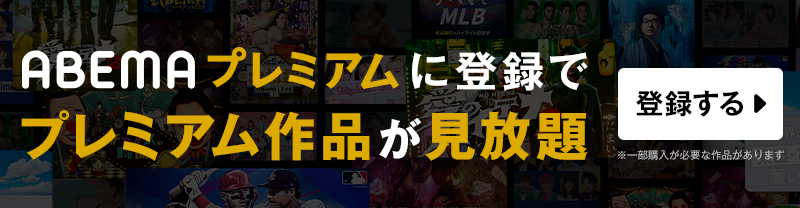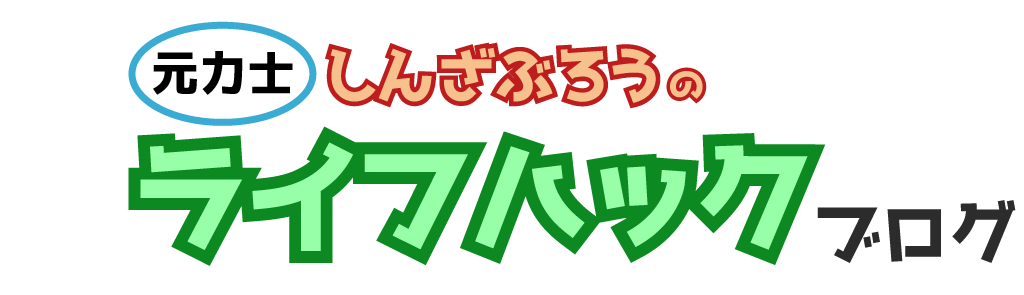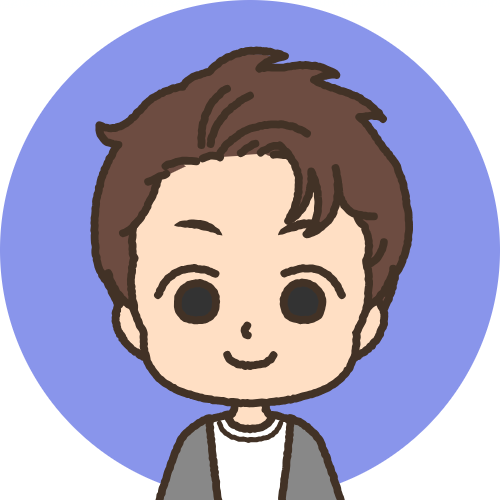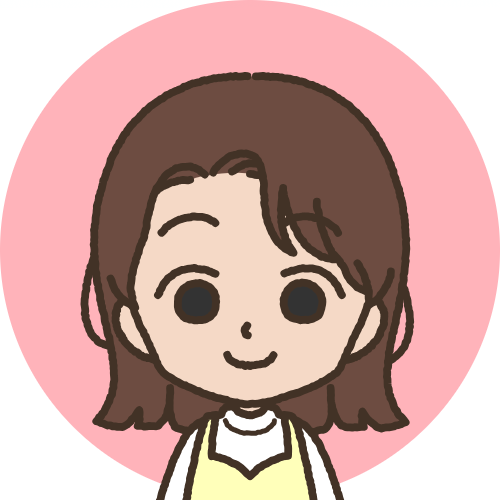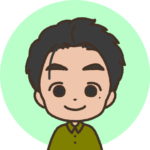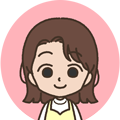蔵前国技館とは?戦後に建設された背景と閉館・跡地の現在まで大特集!
こんにちは!元力士のしんざぶろうです。
「蔵前国技館」その名前を聞けば、昭和の相撲人気を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
1954年の開館から1984年の閉館までの約30年間、東京本場所の舞台として数々の名勝負を生み出し、テレビ中継の普及とともに大相撲を全国へ広げる大きな役割を担いました。
本記事では、蔵前国技館が誕生した背景やその革新性、昭和を彩ったスター力士たち、さらに閉館後の跡地や現在の両国国技館へのつながりまでを、できるだけ分かりやすくご紹介します。
ぜひ最後までお付き合いくださいね。
蔵前国技館って、僕が子どもの頃にテレビで中継されていたはずなんだけど、正直あんまり記憶がないんだよね。いったいどんな場所だったんだろう?
- 蔵前国技館が建てられた理由と、戦後の相撲界が直面した課題
- 蔵前国技館の特徴・革新
- 昭和の黄金期とスター力士(栃若・柏鵬・輪湖)
- 蔵前国技館の閉館と跡地の現在
- 新両国新国技館の誕生と役割
蔵前国技館とは?-戦後の相撲界と会場不足
 蔵前国技館とは、戦後の混乱期に旧両国国技館に代わって大相撲を支えた国技館です。
蔵前国技館とは、戦後の混乱期に旧両国国技館に代わって大相撲を支えた国技館です。
蔵前国技館は、1954年(昭和25年)から1984年(昭和59年)までの約30年間、東京本場所の中心として多くの名勝負を生み出しました。
以下の動画では、蔵前国技館の当時の様子を見ることができます。有名なやきとり工場や相撲茶屋、観客との距離感など、いまでは考えられないほど“手作り感”にあふれた雰囲気が伝わってきます。
動画を見て知ったけど、蔵前国技館の時代から相撲博物館や焼き鳥工場があったんだね!お客さんとの距離もすごく近くて、昔から相撲を楽しむ工夫がいっぱいあったんだなぁ。
ところで、どうして旧両国国技館から蔵前に移ったんだろう?
戦後の相撲界
第二次世界大戦後、相撲界は大きな試練に直面しました。大正から昭和初期にかけて「相撲の殿堂」と呼ばれた旧両国国技館は、戦災や空襲で大きな被害を受け、さらに戦後はGHQに接収され「メモリアルホール」と改称。以降、相撲の興行は許されず、長年本場所を支えてきた舞台を失った日本相撲協会は、開催の場を求めて苦境に立たされました。
一時は明治神宮外苑や浜町の仮設国技館などで本場所を続けていましたが、雨天への対応や収容人数不足といった課題が多く、恒久的な本拠地の必要性がますます強く叫ばれるようになったのです。
旧両国国技館の歴史
〇大鉄傘と呼ばれた初代国技館
1909年(明治42年)、江戸相撲の聖地・回向院の東隣に建設された初代国技館は、鉄柱308本で支えられた大屋根の姿から「大鉄傘(だいてっさん)」の愛称で親しまれました。ヨーロッパ風の大ドーム建築は当時としては画期的で、収容人数は最大13,000人を誇りました。
〇度重なる苦難の時代
1923年(大正12年)の関東大震災、1945年(昭和20年)の東京大空襲などで大きな被害を受けます。そして戦後はGHQに接収され、相撲の舞台が提供できなくなりました。
〇日大講堂として終焉
1952年(昭和27年)に接収が解除され、相撲会場としての再利用も検討されましたが、その頃にはすでに蔵前国技館が建設されており、実現しませんでした。
その後、国際スタジアムを経て1958年(昭和33年)に日本大学に譲渡。「日大講堂」となり、コンサートや講演会の会場として活用されました。しかし老朽化が進み、1983年(昭和58年)に解体。約70年にわたる歴史に幕を閉じました。
新拠点として選ばれた蔵前
戦後の混乱で本拠地を失った相撲界が、新しい舞台として選んだのは…
台東区蔵前の旧東京高等工業学校跡地でした。
場所は隅田川のほとり、江戸時代から勧進相撲が盛んに行われてきた土地柄もあり、相撲文化と深いつながりを持つ地域です。交通の便も比較的良く、観客を多く集められる条件が揃っていたからです。
- 土地の歴史性:江戸時代から勧進相撲が盛んに行われてきた地域で、相撲文化と深いつながりがあった
- 立地条件:都心に近く、路面電車や鉄道でのアクセスも良好で、多くの観客を集めやすい環境だった
- 用地の確保:旧東京高等工業学校の跡地が利用可能で、広い敷地を確保できた
しかし、当時の日本は戦後の混乱期で資材も資金も不足していました。協会は工夫を凝らし、厚木飛行場の格納庫の鉄骨を払い下げてもらい、それを再利用して国技館を建設。
これは「相撲界の知恵と底力」を示す出来事であり、復興の象徴ともなりました。力士や関係者も工事に携わったといわれ、まさに「相撲界総出の復興事業」として地域とともに進められていったのです。
仮設から本設、そして開館へ
1949年(昭和24年)に工事が始まり、翌1950年(昭和25年)にはまず仮設館が完成。雨風をしのぐ程度の建物ではありましたが、久々に自前の会場を得た相撲界は大きな活気を取り戻しました。
その後も工事は続けられ、1954年(昭和29年)9月に本設の蔵前国技館が落成。開館式は同年9月18日に行われ、純和風の壮大な建築が堂々と姿を現しました。
- 1945年(昭和20年)終戦
・旧両国国技館は東京大空襲で被災。終戦後は、GHQに接収され「メモリアルホール」と改称
・旧両国国技館での興行が許されず、明治神宮外苑や後楽園球場など臨時会場でしのぐ - 1949年(昭和24年)
・蔵前の旧東京高等工業学校跡地で蔵前国技館の建設工事が始まる
・資材不足のため、厚木飛行場の払い下げ鉄骨を再利用 - 1950年(昭和25年)
・仮設の蔵前国技館が完成
・簡素な造りながら、久々に自前の会場を持ち、観客の歓声と熱気が相撲界に戻る - 1954年(昭和29年)9月18日
・本設の蔵前国技館が落成、開館式を開催
・純和風の壮大な建築で、以後東京本場所の象徴となる
以降、1984年の閉館まで東京本場所の舞台を支え、相撲ファンの心に深く刻まれることになります。
蔵前国技館の革新性
蔵前国技館は単なる相撲会場にとどまらず、設備と観戦体験の両面で革新をもたらしました。収容人数は約11,000人。外観は城郭を思わせる純和風建築で、内部には近代的な設備を取り入れた独自のスタイルが特徴でした。
とくに大きな変革は「四本柱の撤廃」です。江戸時代から250年以上続いていた土俵上の四本柱は観戦の妨げになるとして取り払われ、吊り天井方式が導入されました。天井からは青・白・赤・黒の四色房が下がり、視界が大きく改善。現在の国技館の原型は、この蔵前時代にすでに完成していたのです。
さらに、当時としては画期的な電光掲示板の設置、場内アナウンスの整備などにより観客体験は大きく向上。ラジオ中継やテレビ放送も普及し、蔵前国技館は「相撲を全国へ届ける発信地」としての役割も担いました。
- 収容人数は約11,000人。外観は城郭風、内部は近代的な設備を備えた独自の建築
- 四本柱を撤去し、吊り天井と四色房を採用。視界が大きく改善し、現在の国技館の原型となった
- 電光掲示板や場内アナウンスを導入。ラジオ・テレビ中継の普及で「相撲を全国に届ける拠点」となった
蔵前国技館での観客体験
蔵前国技館の支度部屋は客席通路に面しており、観客が帰り際に力士とすれ違うこともしばしば。声をかければ笑顔で応じる力士もいて、握手や激励の言葉が自然に飛び交いました。まるで選手と観客が同じ空間を共有しているような、距離の近さが魅力だったのです。
そして取組が佳境に入ると、館内は熱気でいっぱいに。満員御礼の垂れ幕が下がると、土俵を囲む観客から割れんばかりの拍手と歓声が湧き起こり、「これぞ国技館」という一体感を誰もが味わえたのでした。
うわぁー♪ 想像するだけでワクワクしちゃう!力士とすぐ近くですれ違えたり、自然に声援や拍手が飛び交うなんて、本当にお祭りみたい!私も一度でいいから蔵前国技館で観戦してみたかったなぁ〜。
蔵前国技館の黄金時代
1953年(昭和28年)にテレビ中継が始まると、相撲人気は一気に全国へ広がりました。そして翌1954年(昭和29年)には、本設の蔵前国技館が完成し、本場所は再び安定した舞台を得ます。以降、蔵前は大相撲の中心地として、多くの名勝負を生み出すことになりました。
こうして蔵前が賑わいを見せる一方で、日本社会は昭和30年代から40年代にかけて、高度経済成長の真っただ中。娯楽が多様化していくなかでも、大相撲は「国民的スポーツ」として揺るぎない人気を博し、蔵前は全国から観客を集める象徴的な舞台となったのです。
まさに蔵前国技館での相撲人気は、「昭和の黄金期」と呼ぶにふさわしいものとなったのでした。
昭和のスター力士
そんな黄金期を支えたのは、時代ごとに土俵を沸かせたスター力士たちでした。彼らの激しいぶつかり合いと名勝負は、蔵前国技館を「昭和相撲の舞台装置」として不動の存在に押し上げました。
それでは、蔵前時代を象徴する横綱たちを時代ごとに見ていきましょう。
- 栃若時代(とちわかじだい・1950年代/昭和30年代)
小兵ながらも力強く、鋭い技を武器にした栃錦と若乃花が人気を二分。戦後復興期の国民の心をつかみました。特に若乃花は「土俵の鬼」と呼ばれるほど稽古場で厳しかったことでも有名です。 - 柏鵬時代(はくほうじだい・1960年代/昭和30〜40年代)
柏戸と大鵬のライバル関係は「柏鵬ブーム」を生み、大相撲人気を不動のものにしました。「巨人・大鵬・卵焼き」という流行語が生まれるほど、社会的な影響力も絶大でした。 - 輪湖時代(りんこじだい・1970年代/昭和50年代)
学生相撲出身の輪島と、史上最年少横綱の北の湖。個性の違う二人の対決は、蔵前の熱気をさらに高め、昭和の相撲界を盛り上げました。
以下の動画では、栃若時代を築いた「第44代横綱:栃錦」と「第45代横綱:若乃花」の当時の活躍がご覧いただけます。
栃錦も若乃花も、本当に足腰が強いよね。土俵際での粘り方は、現代の相撲ではなかなか見られない迫力だよ。最後まで勝負が分からない展開は観ていてワクワクする♪
特に若乃花の「呼び戻し(仏壇返し)」は、映像で初めて見たけど衝撃だったな。
多彩なイベントの舞台
蔵前国技館は相撲だけにとどまりません。プロレスでは力道山の時代から、アントニオ猪木やジャイアント馬場の熱戦も繰り広げられました。ボクシングでは白井義男や具志堅用高らの世界戦、柔道・剣道の全日本大会も行われ、格闘技の聖地としての顔も持っていました。
さらに、映画「007は二度死ぬ」や、漫画「あしたのジョー」の舞台としても登場。スポーツと大衆文化が交わる象徴的な場所、それが蔵前国技館だったのです。
蔵前国技館の閉館と跡地
東京本場所を支え続けてきた蔵前国技館も、昭和50年代に入ると次第に課題が目立ち始めました。かつては最新鋭といわれた建物でしたが、木材を多用した構造ゆえ老朽化の進行が早く、社会の変化に合わせた改修も十分に行われませんでした。こうした事情から、新国技館を求める声が高まっていきます。
老朽化と立地の制約
蔵前国技館は約11,000人を収容でき、当初は東京でも有数の大規模施設でした。しかし年月とともに老朽化が進み、耐震性や耐火性への不安が指摘されるようになります。
また、1954年(昭和29年)の開館から約17年間(1954〜1971年)は冷暖房設備がなく、夏冬の観戦環境は厳しいものでした。1971年(昭和46年)の改修で冷暖房が導入され快適性は向上しましたが、老朽化の流れを止めることはできません。
さらに、車社会の進展により周辺道路の狭さや駐車場不足も深刻化。観客の利便性は損なわれ、蔵前国技館は次第に「時代に取り残された施設」と見なされるようになったのです。
最後の本場所と閉館
蔵前国技館は、1984年(昭和59年)秋場所を最後に、その歴史に幕を下ろしました。昭和29年の開館から約30年、東京本場所の舞台として数々の名勝負を生み出してきた国技館の閉館は、相撲界にとってひとつの時代の終わりを意味しました。
解体が決まったときには、多くのファンや力士から惜しむ声が寄せられ、「蔵前で相撲を見られなくなる」という喪失感が広がったといいます。
以下の動画では、支度部屋の様子や蔵前国技館での最後の取組となった横綱・隆の里と横綱・千代の富士の対決、そして「さよならセレモニー」の模様をご覧いただけます。蔵前の熱気と温かさを感じられる貴重な映像ですので、ぜひご覧ください。
蔵前国技館の跡地
その後、蔵前国技館の跡地は東京都に売却され、新国技館の建設資金に充てられました。現在は 東京都下水サービス株式会社の施設「蔵前水の館」 となっています。
そして、この施設は一般に開放されており、館内には往年の力士の手形や番付が展示され、訪れる人々に蔵前国技館の記憶を伝えています。
〇「蔵前水の館」見学について
見学は予約制です。
下記電話または公式ホームページから申し込みが必要です。
- 電話受付
03-3241-0944(平日9:00~17:00まで) - 東京都下水サービス株式会社ホームページ
蔵前水の館-下水道施設見学者対応事業
- 住所
東京都台東区蔵前2-1-8 北部下水道事務所敷地内 - アクセス
最寄り駅は「浅草橋」と「蔵前」
・JR総武線「浅草橋」駅から徒歩約10分
・都営浅草線「蔵前」駅から徒歩約5分
・都営大江戸線「蔵前」駅から徒歩約8分
*駐車場はありません。
約30年しか、蔵前国技館は稼働していなかったんだね…。何だかもったいない気もするね。
新両国国技館の誕生
1985年(昭和60年)、蔵前国技館の閉館に伴い、隅田川を渡って“相撲の原点”両国の地に新国技館が完成しました。蔵前跡地の売却益や協会の積立金、国の補助金を組み合わせて建設費(約150億円)をまかない、借入金なしの「無借金竣工」という快挙を達成しています。
収容人数は約11,000人(公称11,098席)。冷暖房やエレベーターを備え、当時としては最新鋭のインフラを誇る恒久アリーナとして誕生しました。蔵前の課題であった耐震性や快適性も改善され、より観客に優しい会場となったのです。
新両国国技館の役割
両国国技館は、大相撲本場所(1月・5月・9月の年間3場所)の舞台であり、館内には「相撲博物館」も併設。相撲の歴史資料を展示し、文化を発信する拠点となっています。
また、多目的ホールとしてプロボクシングやプロレスの興行が行われ、東京2020オリンピックではボクシング競技会場にも使用されました。音楽コンサートや各種イベントも開催され、「国技館=日本文化とエンタメの殿堂」として幅広く親しまれてきました。
両国国技館は1985年の開館から2025年で40周年を迎え、蔵前の稼働期間(1954〜1984年、約30年)を超える歴史を積み重ねてきました。
一方で、建物の老朽化は進み、設備更新の必要性も課題として挙げられています。とはいえ、両国国技館は相撲界の揺るぎない本拠地であり、蔵前から受け継いだ伝統を未来へとどうつないでいくか、今後の取り組みが注目されるところです。
ちなみに、現在の大相撲は両国国技館だけでなく、大阪・古屋・福岡でも本場所が行われています。それぞれの開催地には独自の歴史や特徴があり、年間6場所を通じて大相撲の魅力が味わえるのです。詳しくは、以下の記事でまとめていますので、ぜひご覧ください。

よくある疑問Q&A
Q1.蔵前国技館はなぜ建てられたの?
旧両国国技館が戦災やGHQ接収で使えなくなり、戦後の大相撲本場所を守るために新たに建てられました。蔵前国技館は、まさに「戦後復興を支えた国技館」だったのです。
Q2.蔵前国技館はどこにあった?跡地は現在どうなっている?
所在地は東京都台東区蔵前2-1-1。現在その跡地は「蔵前水の館」となり、一般公開されています。館内では往年の力士の手形や番付が展示され、蔵前国技館の記憶を今に伝えています。
Q3.蔵前国技館跡地で見学できるスポットは?
「蔵前水の館」のほか、蔵前神社では力持ち奉納の伝統が続き、蔵前橋の欄干には力士のレリーフが並んでいます。蔵前を歩けば、今でも「蔵前国技館の現在」と相撲文化の名残を感じることができます。
Q4.蔵前国技館と両国国技館の違いは?
蔵前国技館は戦後復興から昭和の黄金期を支えた「昭和の国技館」。一方、両国国技館は1985年に完成し、平成から令和にかけて大相撲を支えてきた「現代の国技館」です。
蔵前国技館から両国国技館へ舞台が移ったことで、大相撲は新しい時代を迎えました。
まとめ
蔵前国技館は、戦後復興の象徴として誕生し、昭和相撲の黄金期を支えた大舞台でした。四本柱を撤廃した土俵、観客との近い距離感、そしてテレビ中継とともに広がった国民的人気は、まさに「昭和の国技館」と呼ぶにふさわしい存在です。
1985年にその舞台は両国へと移りましたが、蔵前の記憶は今も「蔵前水の館」や地域の文化の中に息づいています。蔵前を知ることは、相撲の歴史を知ることでもあります。
国技館の変遷をたどることで、大相撲が日本文化に果たしてきた役割の大きさを、そっと感じ取っていただければ嬉しいです。
今回も、最後までお読みいただきありがとうございました。
また次回の記事でお会いしましょう。
相撲中継ならABEMAプレミアム一択です
「序ノ口から横綱まで、全取組を観たい」「取組後すぐに見返したい」
「解説の面白さも味わいたい」——
そんな相撲ファンにとって、ABEMAプレミアムは本当にありがたい存在です。
■序ノ口から全取組を完全中継
■広告なしでストレスゼロ
■見逃した取組もすぐ再生
■幕内以外の注目力士も毎日追える
月額1,080円(税込)で、毎場所がもっと楽しくなる。
NHKだけでは物足りない、そんな方にこそぜひ使ってほしいサービスです。