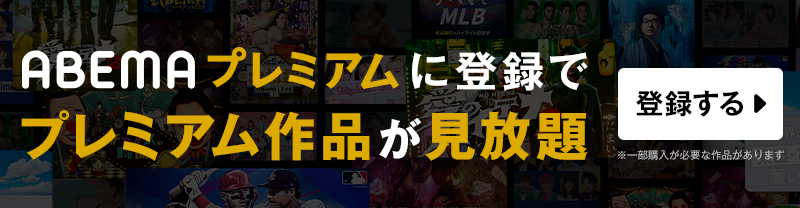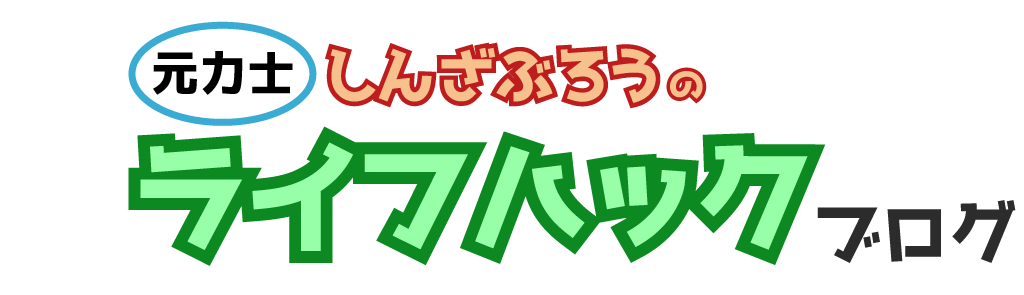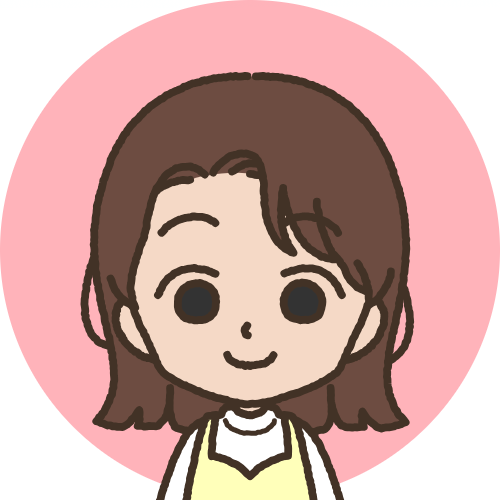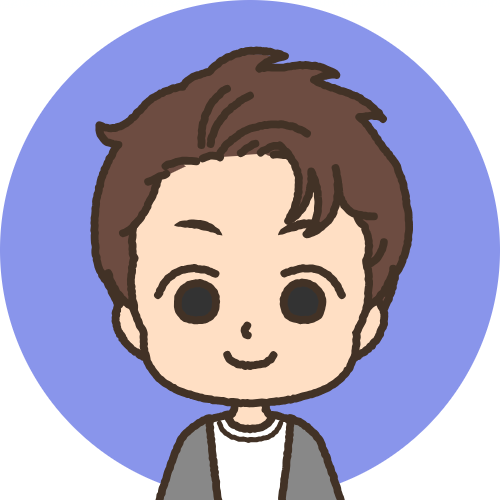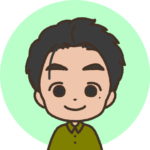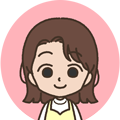弓取式を務める力士の手当や待遇とは?給料との違いや選出基準も解説
僕が化粧まわしを締めたのは、7年間の力士人生でたった一度。それは、前相撲を終え、次の場所から番付に載る力士として披露される「新序出世披露」のときでした。師匠の化粧まわしを借りて土俵に上がったあの瞬間の緊張感と誇らしさは、今でも忘れられません。
でも、幕下以下の力士でありながら、毎場所大銀杏を結い、化粧まわしを締めて土俵に上がれる力士がいるんです。それが弓取式を務める力士。この役割は単なる演出ではなく、相撲の格式や伝統を象徴する大事な儀式で、選ばれた者だけが務めることを許される名誉あるポジションなんですよね。
ただ、その一方で「弓取式を務める力士は関取になれない」なんてジンクスがあったり、長期間務めることで昇進が遅れることもあったり…。相撲界の伝統を支える重要な役割である一方で、少し複雑な側面もあります。
今回は、そんな弓取式の歴史やルール、務める力士の選ばれ方、そして給料事情まで、まるっと解説していきます!
ぜひ最後までお付き合いくださいね。
弓取式を見ると、『あぁ、今日の取り組みも終わったなぁ』ってしみじみしちゃうのよね。結びの一番の後に、あの静かで美しい動きがあると、余韻がじんわり広がる感じがして…
- 弓取式の概要と、本場所や巡業での役割
- 弓取式の歴史的背景と起源に関する諸説
- 弓取式を務める力士の選出基準と待遇
- 弓取式を務める力士の収入と経済的な側面
- 弓取式にまつわるジンクスと、それが覆された事例
弓取式とは?

弓取式(ゆみとりしき)は、大相撲の本場所において…
結びの一番の勝者に代わり、作法を心得た力士が弓を受け取り、勝者の舞を披露する儀式
こうしたものだとお考えください。
そして、その日の全取組が終了した後、「打ち出し」の直前に行われるのも特徴です。
なお、現在のように弓取式が本場所中毎日行われるようになったのは、1952年(昭和27年)からで、それ以前は千秋楽のみに実施されていました。しかし、華麗な弓さばきをより多くの観客に楽しんでもらうことを目的に、ファンサービスの一環として毎日披露されるようになったのです。
弓取式の魅力は、静かな中にも力強さがあり、土俵を締めくくる格式の高さにあります。しかし、本場所ではNHKの中継でも最後まで映されることが少なく、目にする機会は限られています。
そこで、実際に弓取式の様子をご覧いただきたいと思います。
本場所の映像はありませんが、巡業でも観客に向けて披露されており、日本相撲協会の公式Xでその様子が紹介されています。今回は、冬巡業・沖縄場所で撮影された弓取式の動画をご紹介します。本場所とは異なる雰囲気ですが、弓の動きや所作の美しさをじっくりご覧ください。
<冬巡業 #沖縄場所 >
弓取式。
沖縄県宜野湾市出身、立浪部屋の立王尚。#sumo #相撲 #巡業 pic.twitter.com/iwlyx1gAG0— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) December 21, 2024
弓を落した場合
弓取式では力強く弓を振るため、時には誤って弓を落としてしまうこともあります。その際、力士は土俵に手をつかないように足で弓を跳ね上げ、手で受け取るのが作法とされています。
これは、弓取式が勝者の代理で行われる儀式であるため、「土俵に手をつく=負け」を意味することを避けるためです。
万が一、弓が土俵の外へ落ちてしまった場合は、「呼出し」が弓を拾い、土俵に戻します。その間、弓取力士は四股を踏んで待ち、弓が土俵に置かれた後に、作法に従って拾い上げます。
弓取式の歴史
この儀式の起源は平安時代にまで遡り、宮廷行事であった「相撲節会(すまいのせちえ)」に由来すると考えられています。
当時、勝利した力士には褒美として弓矢と弦が与えられ、それを立会役(現在の行司にあたる)が背負い、舞を披露する習わしがあったとされています。しかしながら、これが現在の弓取式に直接つながっているかどうかについては諸説あり、明確には判明していません。
織田信長が起源とする説
織田信長が催した相撲大会で勝者に弓を授けたという説が「古今相撲大全」や「相撲御覧記」に記されいます。これが最も古い記述とされていますが、「信長公記」には記述がなく、信憑性には疑問が残っています。
現在の弓取式の原型が確立されたのは、1791年(寛政3年)のことです。4代目横綱・谷風梶之助が徳川家斉の上覧相撲(将軍が観戦する相撲)において、土俵上で弓を受け取り、それを振りかざしたことが始まりとされています。この動作が儀式としての形式を整え、今日の弓取式へと発展しました。
このように、弓取式は単なる儀式にとどまらず、勝者を称える象徴的な舞であり、同時に相撲の格式を示す伝統的な所作のひとつとして大切にされています。
弓取式を行う力士の選出基準
弓取式を行う力士は、通常、横綱と同じ部屋の幕下以下の力士から選ばれます。横綱が休場している場合や空位となる場合は、大関の部屋または一門から選ばれることになります。
また、弓を巧みに操ることのできる力士が行う必要があるため、1人の力士が長期にわたって務めることが多くなる傾向にあります。
- 横綱と同じ部屋の幕下以下の力士から選ばれる。
- 横綱が不在の場合、大関の部屋または一門から選ばれる。
聡ノ富士と最多記録
弓取式の役割は、単なる儀式ではなく、格式ある技術を伴う重要な役目です。そのため、一度任された力士は長く務めることが多く、弓の扱いや所作を習得した者が交代することなく続ける傾向にあります。
そんな弓取式の世界で、圧倒的な記録を打ち立てた力士をご紹介いたします。
それは、
聡ノ富士 久志さん(さとのふじ ひさし)です。
*以下敬称略
- 本名:松岡 久志(まつおか ひさし)
- 生年月日:1977年4月15日(47歳/2025年2月現在)
- 初土俵:1996年1月場所
- 2025年初場所番付:東序二段72枚目
- 最高位:東幕下55枚目
聡ノ富士は、2013年1月場所から長年にわたり弓取式を務め続け、2024年7月に「江戸の華重信(えどのはなしげのぶ)」が持つ最多記録637回に並び、翌18日には638回目の弓取式を披露し、単独最多記録を樹立したことで話題になりました。
この記録をスポニチが記事にしており、以下がその内容とリンクです。参考にしてみてください。
序二段の聡ノ富士(47=伊勢ケ浜部屋)が結びの1番の後に通算637回目の弓取り式を行い、「輪湖時代」の名弓取りだった江戸の華の持つ歴代最多記録に並んだ。
しかし、同部屋である「横綱・照ノ富士」が2025年1月場所を最後に引退を表明したことにより、聡ノ富士が弓取式を務める機会はなくなる可能性が高いです。
とはいえ、彼が積み重ねてきた記録と功績は、相撲界において大きな意味を持ち、今後の弓取力士にとっても一つの指標となるでしょう。
また、こちらが聡ノ富士の弓取式です。日本相撲協会の公式Xで公開されている動画で、本場所ではなく巡業中のものですが、その華麗な所作をぜひご覧ください。
<春巡業 #ぐんま場所 >
弓取式は聡ノ富士。次回の巡業は4月25日に千葉県木更津市で行われます。#sumo #相撲 #前橋 pic.twitter.com/u1WZHvLEPJ
— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) April 21, 2024
弓取力士って、自分の部屋に横綱や大関がいないと選ばれる可能性が低いのね。そう考えると、聡ノ富士さんの最多記録は、そういう外的要因や巡り合わせに恵まれたとも言えるわね。
【追記】聡ノ富士、弓取式最多記録を残して引退へ
2025年夏場所を最後に、弓取式の最多出場記録を持つ聡ノ富士が引退を表明しました。西序二段100枚目で迎えた14日目、最後の取組を終えた聡ノ富士は「もうおなかいっぱい。やりきった感が強いので、すっきりしています」と語り、29年間の力士人生に幕を下ろしました。
彼は2013年初場所から弓取式を務め、2024年には歴代最多となる638回の所作を披露。その記録と姿勢は、相撲界の歴史に深く刻まれることとなりました。
引退後は、東京都内で飲食業に携わる予定とされています。その長年の貢献には、深い感謝と敬意が寄せられています。
西序二段100枚目の聡ノ富士はこの日、同99枚目の隈錦(21)との最後の取組を終え、土俵に別れを告げた。「十分やりきりました。もうおなかいっぱいです。やりきった感が強いので、本当にすっきりしています」と話した。
弓取式を行う力士の給料
弓取式を行う力士に支払われるのは「手当」であり、関取のような「給料」ではありません。力士に月給が支給されるのは十両以上の関取のみであり、幕下以下の力士は基本的に手当のみで生活しています。
では、弓取式の手当はいくらなのかというと、
1場所につき9万円
という情報が有力です。
ただし、日本相撲協会の公式発表はなく、あくまで参考情報として考えてください。
そして、年間に換算すると、9万円 × 6場所 = 54万円となります。幕下以下の力士にとっては大きな収入源となるため、弓取式を務めることは経済的なメリットがあるといえます。
以下は、力士の階級ごとの給料をまとめた表です。参考にしてください。
*幕下以下は場所毎の支給で、正確には手当として支給されます。
| 収入の種類 | 番付名 | 金額 |
|---|---|---|
| 月給 | 横綱 | 300万円 |
| 大関 | 250万円 | |
| 関脇 | 180万円 | |
| 小結 | 180万円 | |
| 前頭 | 140万円 | |
| 十両 | 110万円 | |
| 本場所ごとに支給 基本手当/年6回 |
幕下 | 16万5千円 |
| 三段目 | 11万円 | |
| 序二段 | 8万8千円 | |
| 序の口 | 7万7千円 |
なお、幕下以下の力士を含めた力士の収入については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。力士の収入事情をより深く知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

弓取式を行う力士の待遇
弓取式を行う力士には、手当の支給だけでなく、他の幕下以下の力士には許されない特別な待遇が与えられています。これらの待遇は、弓取式の役割が格式のある伝統的な儀式であることを示しており、弓取力士としての誇りにもつながっています。
大銀杏が結える
通常、幕下以下の力士はちょんまげを結いますが、弓取力士は特別に大銀杏を結うことが許されています。これは、弓取式が格式高い儀式であり、土俵上での所作を美しく見せるために認められた特例です。
大銀杏を結うことができるのは基本的に関取以上の力士のみであり、幕下以下の力士にとっては名誉な待遇の一つといえます。
化粧まわし
幕下以下の力士は通常、化粧まわしを着用することは許されていません。しかし、弓取力士は例外として協会所有の化粧まわしを締めて弓取式を務めます。これにより、儀式としての格式がさらに高まり、観客にも視覚的な華やかさを提供しています。
なお、大阪場所(春場所)では「東西会」が所有する特別な化粧まわしが使用される点も特徴です。これは、大阪ならではの伝統として定着しており、他の本場所とは異なる趣があります。
本場所の最後を締めくくる名誉ある役割
弓取式は、単なる儀式ではなく、大相撲の一日の締めくくりを飾る重要な役割を担っています。結びの一番の直後に行われるため、観客の注目を集めるだけでなく、力士自身にとっても名誉な場面となります。
特に千秋楽では、その場所の最後の所作として弓取式が披露されるため、より厳粛な雰囲気が漂います。このように、弓取式を務める力士は、一日の最後に土俵に立つ特権を持つことになり、相撲界において特別な存在であることを象徴しています。
千秋楽で幕内の優勝決定戦が行われる場合、弓取式は決定戦の前に実施されます。つまり、その日の本割(本場所の公式取組)の最後に弓取式が行われることになります。
弓取式のジンクス
かつて、弓取式を務めた力士には「関取になれない」というジンクスがありました。その理由として、幕下以下の身分でありながら安定した手当を得られることで、出世への意欲が低下するという見方があったようです。
*元力士としての見解
上記に加えて、弓取式は横綱や大関の取り組み直後に行われるため、力士にとって憧れの舞台に立つ機会にもなります。
そのため、疑似的ではあるものの、大舞台の雰囲気を味わうことで関取への憧れや出世欲が薄れることもあるのではないかと考えられます。
しかし、このジンクスは1990年に九重部屋の巴富士が十両へ昇進し、最終的には小結まで出世を果たしたことで覆されました。その後も、皇牙(2006年に十両昇進)など、関取になった例が存在します。
現在では、このジンクスは次第に薄れつつありますが、長期間弓取式を務める力士が多いため、結果的に昇進が遅れるケースも少なくありません。
弓取式の待遇は確かに力士にとっては光栄だけど、このジンクスは何だか気になっちゃって、複雑だなぁ。自分がやるとしたら、ちょっと考えちゃうかも…。
まとめ
こうして見てみると、弓取式はただの儀式ではなく、相撲の格式を示す大切な所作であり、長い歴史の中で受け継がれてきたものだということが分かります。しかも、大銀杏を結い、化粧まわしを締めて土俵に立てる数少ない幕下以下の力士として、その名誉と責任を背負う特別な役割でもあるんですよね。
ただ、長く務めることで出世が遅れることもあり、力士としてはちょっと複雑な立ち位置になることも。とはいえ、弓取式を通じて相撲の伝統を守り続けた力士たちの努力は、確実に相撲界に刻まれています。
これから相撲を見るときは、結びの一番が終わった後の弓取式にもぜひ注目してみてください!その日の取組を締めくくる、力士たちの美しい所作や凛々しい姿を、じっくり楽しんでもらえたらと思います。
今回も、最後までお読みいただきありがとうございました。
また、次回の記事でお会いしましょう。
相撲中継ならABEMAプレミアム一択です
「序ノ口から横綱まで、全取組を観たい」「取組後すぐに見返したい」
「解説の面白さも味わいたい」——
そんな相撲ファンにとって、ABEMAプレミアムは本当にありがたい存在です。
■序ノ口から全取組を完全中継
■広告なしでストレスゼロ
■見逃した取組もすぐ再生
■幕内以外の注目力士も毎日追える
月額1,080円(税込)で、毎場所がもっと楽しくなる。
NHKだけでは物足りない、そんな方にこそぜひ使ってほしいサービスです。